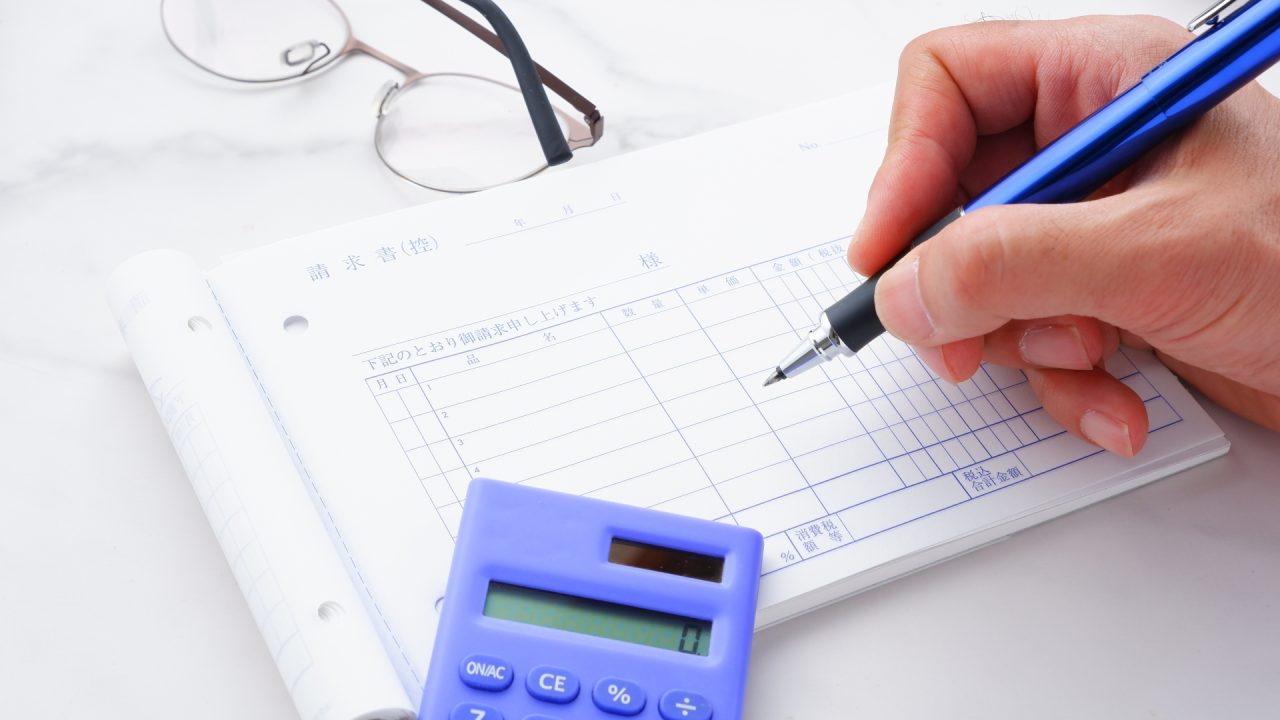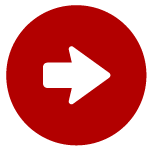水増し請求とは、実際に払う必要のない費用を請求することです。
虚偽の請求書を発行するため、背任罪と詐欺罪が該当し、内容によってはその両方が処せられる場合があります。
従業員に損害賠償を請求するなど法的手段を取りたい場合、被害を受けた企業側は、客観性と正確性が担保された証拠を確保する必要があります。
この記事では、水増し請求の内容とよくあるケース、水増し請求が行われた場合に証拠を確保する方法について解説しています。
\匿名相談に対応 法人様はWeb打ち合わせも可能/
目次
下請けを発注した際に起こりやすい水増し請求の内容
料金や経費など、実際の支出額よりも多く請求して、差額分を横領する行為を「水増し請求」と言います。
精神的プレッシャーを与え承認を迫るケースや、下請け会社と元請け会社の従業員が協力して、水増し請求するケースも増加しています。
建設業で実際に行われた水増し請求のケースを挙げると、下請け会社の従業員が元請け会社の従業員と、事前に相談・結託した上で、実際にかかった工事金額よりも多額の金額を請求、支払いをさせます。
業務上横領罪でなく詐欺罪に該当
下請け企業による水増し請求は、形式上は正規の請求書が発行されているため、単なる経理ミスのように見えることがあります。しかし、実態が虚偽の業務報告や費用請求である場合は、刑法上の詐欺罪(刑法第246条)が適用される可能性があります。業務上横領罪は「自己の占有する他人の物を横領」した場合に適用されるため、第三者である下請け業者による虚偽請求はこの罪には該当しません。
なお、発注者側の従業員が下請けと共謀していた場合、共犯関係が成立する可能性があり、その際には背任罪や証拠隠滅罪などの追加検討も必要となります。
\匿名相談に対応 法人様はWeb打ち合わせも可能/
水増し請求でよくある事例
水増し請求が発生しやすいケースとして、以下のような事例があります。
出来高査定や外注費に上乗せされている
建設業・製造業・メーカーなどの業界では、下請け会社を利用することが多い分、水増し請求の被害も相次いでいます。
例えば建設業では、毎月の工事の進捗や出来高に応じて支払われる「出来高査定」が採用されていることが多いです。
これは建設工事中の中間払いを行うための査定ですが、システム上、工事原価の計上や出来高の架空計上など、不正が発生しやすくなることは否定できません。
水増し請求にキックバックの手法が使用される
キックバックとは、売上額や取引額の一定基準を超えた業者に対して、支払いの一部を支払い人に戻すことを言います。
似たような言葉に「リベート」がありますが、キックバックはやや否定的な印象があるため、リベートの方が一般的に使用されます。
違法なキックバックの内容として、以下のようなケースがあります。
- メーカーの担当者Aが取引先のBと結託し、本来なら1,000万円で発注するところ、水増しした1,200万円の見積もりを作り100万円ずつAとBが私的に受け取った
違法なキックバックは建設業関係なく、どの企業であっても発生する可能性があり、水増ししたキックバックがされた場合は会社に損害が発生します。
下請け側で発生した実費を証明する領収書を改ざんしたり、実際には発生していない出張費・交通費などを追加請求したりするケースです。過去に支払実績がある場合でも、逐一確認を怠ると長期間にわたり見逃されるリスクがあります。
下請け代金を水増し請求する
下請け企業との取引が「定額制契約」であっても、契約期間中に「人件費の高騰」「資材費の上昇」といった外的要因を理由に、再三にわたり請求金額を上乗せしてくるケースがあります。明確な根拠や協議を経ずに請求額を変動させることは、実態に基づかない水増し請求である可能性があるため注意が必要です。
とくに以下のような手口が組み合わされている場合、継続的かつ意図的な不正行為である疑いも生じやすくなります。
出来高査定の過大報告
工事や制作物の進捗に応じて報酬を支払う「出来高払い」契約において、実際の進捗よりも多くの作業が完了しているように報告する手口です。実地確認が難しい業務ほど虚偽報告が行われやすくなります。
架空外注・不要作業の請求
実在しない外注先を名目上設定して外注費を計上したり、必要のない作業工程を追加して請求するなど、実態のない費用項目を組み込む方法です。帳簿上は正当な経費のように見せかけることが多いため、注意深い検証が求められます。
実費経費の水増し
交通費、宿泊費、消耗品費などの実費経費を過大に記載して請求する行為です。領収書の偽造や、実際には発生していない出張費の計上なども含まれます。
正当性のない単価改定
発注前に合意された単価条件を守らず、「昨今の物価上昇」や「相場変動」などを理由に一方的に単価を引き上げる請求が繰り返される場合もあります。契約書に改定ルールが明記されていない場合、こうした請求の妥当性はきわめて低くなります。
このように、本来は払うべきではない金額が含まれた請求は、損害を与えたとして詐欺罪や背任罪に当たる可能性があります。社内外の複数人が関わっている場合もあるため、スマホやパソコンのメールのやり取りなどが証拠となる場合もあります。
ただし、電子端末上のデータは改ざんが容易なため、外付け機器にコピーしたり、印刷しただけでは証拠として認められない場合もあります。このようなデータを法的証拠として取得するには、専門家に相談することをおすすめします。
フォレンジック調査会社のデジタルデータフォレンジックでは、電子端末内を解析し、水増し請求の証拠がないか調査します。証拠隠滅されていた場合も対応できる場合があるため、まずはお気軽にご相談ください。匿名の相談も受け付けております。
水増し請求が発覚した場合の流れ
水増し請求がされていたことが発覚し、法的手段を取る場合は、証拠の確保が必要になります。
以下の方法で証拠を確保するようにしましょう。
社内調査で下請けに水増請求した証拠を確保する
証拠を確保するためには社内調査が必要になり、確認するものとしては以下の物が挙げられます。
- 請求書や領収書などの帳簿類
- 会議録や稟議書などの書類
- 目撃者や関係者による証言
- メールやチャットなどの通信履歴
- パソコンに保存された請求書のデータ
水増し請求については、証拠を隠蔽される場合もあるため慎重に調査を進める必要があります。中には請求書を改ざんしている場合もあるため、詳細な調査をするために調査会社に依頼するなど、第三者を交えることが望ましいです。
また、とくにメールや情報などのデータに関する証拠は、自社のみでの証拠収集は難しく、専門知識が無い中での調査はほとんど不可能です。そのため、データに関する情報を確保したい場合は調査会社に依頼しましょう。
調査会社に水増し請求の証拠収集を相談する
最近は請求書などがパソコン上で作成されることもあり、金額が水増しされた請求書などのデータも法的証拠として認められています。
しかし、請求書などのデータは簡単に金額を改ざんできてしまうため、単にデータを保存しただけでは証拠隠滅やねつ造の可能性がないことを証明できません。
そこで、電子データを法的証拠とするには「フォレンジック調査」を行います。
「フォレンジック調査」とは、デジタル機器から法的証拠に関わる情報を抽出する技術を用いた調査です。削除されたファイル履歴の内容や、パソコン内の不正なファイル、社内で許可されていないUSBの接続履歴、メール履歴調査など、これら以外にも調査項目は複数存在し、水増し請求を訴えたい場合に使用できる証拠を電子端末上から確保できる場合があります。
調査結果に応じて水増し請求の関係者の懲戒処分を行う
下請け企業との不正に社内の従業員が関与していた場合、その行為が就業規則や社内倫理規程に反するものであれば、懲戒処分の検討が必要となります。特に、見返りを得る目的で下請けに水増し請求を容認したり、虚偽の承認を繰り返していた場合は、組織的な背任行為とみなされる可能性もあります。
ただし、懲戒処分には以下のような法的・実務的な留意点があります。
- 懲戒の種類と段階を区別する必要がある
懲戒には「けん責」「減給」「出勤停止」「降格」「諭旨解雇」「懲戒解雇」など段階がありますが、処分の重さは違反の内容・悪質性・過去の勤務態度等により個別に判断することが求められます。 - 就業規則への根拠明記が必要
たとえば「不正請求への加担」や「会社の名誉を著しく傷つける行為」が懲戒事由に該当する場合、就業規則に該当条項がなければ処分が無効となるリスクがあります。 - 処分までの手続きも重要
突然の懲戒処分は「不当処分」として訴訟になることもあるため、弁明の機会を与える「事前聴聞」や、社内懲戒委員会による審査など、慎重なプロセスが求められます。 - 証拠の裏付けが不可欠
処分の合理性を裏付けるためには、業務端末の操作ログ、承認履歴、社内チャットやメールの内容、金銭授受の記録など、客観的証拠を事前に整備しておく必要があります。
なお、処分の前提として、本人の関与を一方的に断定せず、可能な限り事実関係を正確に把握したうえで、懲戒の合理性と社会的相当性を満たす判断を行うことが重要です。場合によっては、第三者委員会による客観的な調査結果をもとに処分を決定する方法も検討されます。
水増し請求が悪質な場合警察に被害届の提出を行う
水増し請求の被害額が高額であったり、下請け企業と社内関係者が共謀して不正を継続していたような場合には、刑法上の詐欺罪や背任罪が成立する可能性があり、警察への通報や刑事告訴が検討されます。
ただし、刑事手続に進むには、証拠が適切に保全されていることが前提となります。捜査の進行に耐えうる記録の整備や、社内調査の客観性・中立性も重要なポイントとなります。
以下に、警察への相談や被害届の提出を検討する際の実務的ポイントを整理します。
| ポイント | 具体的な留意点 |
|---|---|
| 1. 証拠の確保 | 請求書、業務報告書、社内メール、PCログ、承認履歴などを法的証拠として保存。フォレンジック調査などによる取得が有効。 |
| 2. 社内判断の妥当性 | 不正が組織的に行われていたか、役員・従業員が関与していたかなど、社内調査報告書として文書化しておく。 |
| 3. 外部連携 | 顧問弁護士や法務部と連携して刑事手続の妥当性を判断。通報や告訴のタイミングも慎重に検討する。 |
| 4. 通報の準備 | 刑事告訴書や被害届には、時系列・関係者・被害金額などを明確に記載する必要がある。 |
なお、警察が捜査に着手するかどうかは、案件の内容や証拠の精度、被害額の大きさなどにより異なります。捜査当局への対応を誤ると、二次的な混乱や報道リスクも生じ得るため、社内外の専門家と十分に協議したうえで進めることが望まれます。
水増し請求の証拠を確保したい場合は調査会社に依頼する

社内不正・横領・情報持ち出し・職務怠慢のような問題が発生した場合、どのような経路で、どのような情報が漏えいしたのか、被害の全容を正確に把握する必要があります。適切な調査によって原因究明を行うためにも、フォレンジック調査の専門家に相談することが重要です。
特に、法的手続きが絡むケースや被害が広範囲に及ぶ場合は、専門家の力を借りることで被害の最小化と信頼性の高い証拠の収集が可能です。
>情報漏えい時の個人情報保護委員会への報告義務とは?詳しく解説
当社では、インシデント対応のプロが初動対応から、専門設備でのネットワークや端末の調査・解析、調査報告書の提出、ならびに報告会によって問題の解決を徹底サポートします。
フォレンジックサービスの流れや料金については下記からご確認ください。
【初めての方へ】フォレンジックサービスについて詳しくご紹介
【サービスの流れ】どこまで無料? 調査にかかる期間は? サービスの流れをご紹介
【料金について】調査にかかる費用やお支払方法について
【会社概要】当社へのアクセス情報や機器のお預かりについて
デジタルデータフォレンジックの強み
デジタルデータフォレンジックは、迅速な対応と確実な証拠収集で、お客様の安全と安心を支える専門業者です。デジタルデータフォレンジックの強みをご紹介します。
累計相談件数39,451件以上のご相談実績
官公庁・上場企業・大手保険会社・法律事務所・監査法人等から個人様まで幅広い支持をいただいており、累積39,451件以上(※1)のご相談実績があります。また、警察・捜査機関から累計395件以上(※2)のご相談実績があり、多数の感謝状をいただいています。
(※1)集計期間:2016年9月1日~
(※2)集計機関:2017年8月1日~
国内最大規模の最新設備・技術
自社内に40名以上の専門エンジニアが在籍し、14年連続国内売上No.1のデータ復旧技術(※3)とフォレンジック技術でお客様の問題解決をサポートできます。多種多様な調査依頼にお応えするため、世界各国から最新鋭の調査・解析ツールや復旧設備を導入しています。
(※3)第三者機関による、データ復旧サービスでの売上の調査結果に基づく。(2007年~2017年)
24時間365日スピード対応
緊急性の高いインシデントにもいち早く対応できるよう24時間365日受付しております。
ご相談から最短30分で初動対応のWeb打合せを開催・即日現地駆けつけの対応も可能です。(法人様限定)自社内に調査ラボを持つからこそ提供できる迅速な対応を多数のお客様にご評価いただいています。
デジタルデータフォレンジックでは、相談から初期診断・お見積りまで24時間365日体制で無料でご案内しています。今すぐ専門のアドバイザーへ相談することをおすすめします。
第三者委員会におけるフォレンジックの重要性
企業不祥事の調査では、表面的なヒアリングだけでは事実関係を十分に把握できないケースも少なくありません。特に、やり取りや操作の記録といったデジタルデータに証拠が残る現代では、専門的な技術と知見が求められます。
日本弁護士連合会の『企業等不祥事における第三者委員会ガイドライン』でも、「必要に応じてデジタル調査の専門家に調査への参加を求めるべき」と明記されており、フォレンジック調査は、公的にも重要なアプローチの一つとして位置付けられています。
調査の初動段階から、フォレンジックの活用を視野に入れることが、的確な対応への第一歩となります。
フォレンジック調査が有効な場面
フォレンジック技術は、社内不正の“見えにくい痕跡”を可視化し、証拠に基づく判断を支援します。たとえば、以下のような目的で活用されます。
| フォレンジック技術でできること | フォレンジック調査の活用目的 |
|---|---|
| 削除済みファイルの復元 | 証拠隠滅を試みた痕跡を追跡 |
| メール・チャットの解析 | 内部のやりとりから動機や指示系統を明らかにする |
| アクセスログの調査 | 不正操作の実行者や実行時間を特定する |
| 記録改ざんの検出 | 会計不正や品質データ改ざんの証拠を技術的に裏付ける |
これらはどれも、高度な技術と専門的な解析スキルが求められる領域であり、専門家による対応が不可欠です。
「第三者委員会でフォレンジック調査をどう活用できるのか」について詳しくはこちらのコラムをご覧ください。

専門調査会社への相談は、早期対応への一歩
当社では、第三者委員会との連携や社内調査の支援など、状況に応じた柔軟な対応が可能です。不正の兆候に気づいたときや、調査の進め方に迷ったときには、まずは専門の調査会社へご相談ください。初動の一手が、被害拡大を防ぎ、組織の信頼を守ることにつながります。
DDFの調査事例
こちらではDDFにご相談されたお客様の調査事例を紹介します。
相談内容
取引先と結託して水増請求を行っている社員がいるので、実態解明の調査をしてほしい
調査内容
- メール履歴調査
- 通話履歴調査
- アプリケーション調査
以上の調査を行った結果、メールやアプリケーションに水増し請求に関連しているとされる人物との不審なやりとりが確認されました。
下請けの水増し請求を防止する方法
水増し請求の発生を未然に防ぐには、請求プロセスの透明化と定期的なチェック体制の整備が重要です。ここでは、予防のために有効とされる実務的な対策を紹介します。
請求内容と実績の「突合チェック」を徹底する
請求書の内容と、実際の業務進捗・納品物・作業報告などを突合せて確認する体制を整えることが基本です。二重チェックの仕組みを導入し、担当部署と会計部門で確認を分担すると、不正の見落としを防ぎやすくなります。
第三者による定期的な「スポット監査」を実施する
内部監査部門や外部会計士による抜き打ちのレビューを定期的に行うことで、不正の抑止力になります。とくに過去に不審な請求があった取引先に対しては、重点的に実施すると効果的です。
契約前に「成果物の明確化」と「単価基準」を設定する
請求内容の曖昧さが水増しの温床になるため、業務委託契約では成果物の定義・単価算出根拠・作業条件などを明文化しておくことが大切です。業務内容が抽象的な場合は、都度協議のルールも記載しておきましょう。
「請求履歴のデータ分析」で異常値を早期検知する
請求金額の推移や取引傾向を定期的に分析することで、異常値やパターンの変化を可視化できます。急な増額や項目の追加が見られた場合は、追加調査のきっかけになります。
よくある質問
対応内容・期間などにより変動いたします。
詳細なお見積もりについてはお気軽にお問い合わせください。
専門のアドバイザーがお客様の状況を伺い、概算の見積りと納期をお伝えいたします。
可能です。当社は特定の休業日はございません。緊急度の高い場合も迅速に対応できるように、365日年中無休で対応いたしますので、土日祝日でもご相談下さい。
もちろん可能です。お客様の重要なデータをお取り扱いするにあたり、当社では機密保持誓約書ををお渡しし、機器やデータの取り扱いについても徹底管理を行っております。また当社では、プライバシーの保護を最優先に考えており、情報セキュリティの国際規格(ISO24001)およびPマークも取得しています。法人様、個人様に関わらず、匿名での相談も受け付けておりますので、安心してご相談ください。