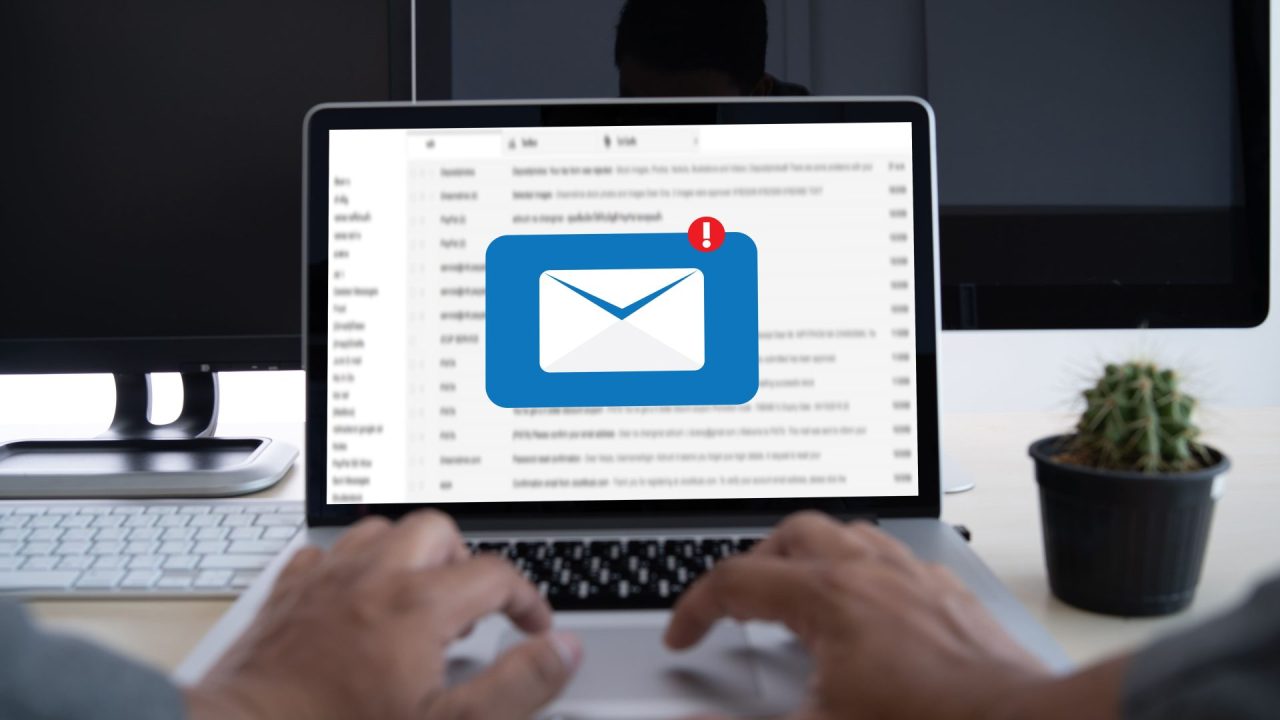退職という節目に際して、見落とされがちなリスクの一つが「データの削除」です。退職者による意図的・非意図的なファイル削除が企業活動に及ぼす影響は深刻であり、法的責任問題に発展するケースも後を絶ちません。本記事では、退職時のデータ削除を巡るリスクの全貌と、企業・従業員が取るべき具体的な対策について詳しく解説します。
社内不正調査のご相談がすぐに必要な方は、匿名でのご相談にも対応しております。法人のお客様には、Web打ち合わせでのご対応も可能ですので、以下の連絡先よりお気軽にご連絡ください。
目次
退職時に生じるデータ削除リスクの全体像
企業の資産である情報が退職者によって削除されることで、業務停止・損害・法的トラブルに発展する可能性があります。
証拠隠滅のための削除
退職直前に不正行為の証拠を隠滅する目的でファイルを削除するケースがあります。業務日報、取引記録、ログデータなどが削除されると、不正の追跡が困難になります。
悪意ある報復・嫌がらせ
会社への不満やトラブルを抱えた従業員が、意図的に重要データを削除する報復的行為を行うことがあります。サーバーデータ、顧客リスト、ノウハウ集が標的になります。
個人利用目的でのデータ改ざん
営業資料や技術文書を自身のポートフォリオとして再利用するため、改ざんまたはコピー後に削除する事例も存在します。これは営業秘密の漏洩にもつながります。
操作ミスによる削除
意図的ではなく、退職前のファイル整理中に誤って必要なデータを削除してしまうことも。バックアップ体制がなければ、被害は甚大です。
セキュリティ対策の不備
従業員のアクセス権限やログ監視が徹底されていない場合、退職直前にデータ操作が可能な状態が残っていることがあります。
削除後に発覚した被害の拡大
ファイル削除はすぐに表面化せず、後日業務に支障が出た際に初めて判明することも。すでに退職者が連絡不能となっている場合、復旧はより困難になります。
退職者によるデータ削除が発覚した場合の対処法
退職者によるデータ削除がすでに発生した場合、被害拡大を防ぎ、証拠を保全するためには、スピーディかつ正確な対応が求められます。
被害の範囲と影響を特定
まず最初に行うべきは、「どのデータが」「どの時点で」「どの端末から」削除されたのかを明確にすることです。
- サーバーやPC内のファイルの整合性を確認する。
- 削除されたフォルダやファイル名、削除日時を特定する。
- 業務・売上・顧客対応への影響を部門単位でリストアップ。
証拠の確保とログ保全
証拠を損なわないよう、削除が疑われる端末・サーバーには極力触れず、アクセスログやシステムログの取得に専念します。
- アクセスログ、ファイル操作ログをすぐにバックアップ。
- 該当端末の使用を中止し、OSごとイメージ取得(論理コピー)。
- 従業員のメールやチャット履歴も保存しておく。
フォレンジック調査の依頼
ログだけで原因を特定するのは難しく、社内対応では証拠性の観点から不十分です。速やかにデジタル・フォレンジック調査会社に相談してください。
社内や個人でフォレンジック調査を完結させるのは、証拠の観点からリスクが高いことを強く認識し、専門業者への依頼を徹底してください。
- 削除操作が行われた日時、ユーザー名を特定。
- 削除前のファイル名やデータ構成を復元。
- USB使用、メール添付、クラウド転送の有無を解析。
法的手段の準備
損害が明確な場合は、退職者に対する損害賠償請求や刑事告訴の検討が必要です。
- 弁護士と相談し、法的責任の可否を確認する。
- 就業規則や誓約書の違反有無を精査する。
- 被害額の算出根拠を明文化しておく。
社内および顧客への報告体制
削除対象に個人情報や顧客関連データが含まれていた場合、個人情報保護法および信頼維持の観点から速やかな報告が必要です。
- 被害概要を役員・法務・情報管理部門で共有。
- 個人情報漏洩がある場合、個人情報保護委員会に報告。
- 顧客や取引先に対して謝罪文と対応策を提示。
再発防止策の実施
同様のインシデントを防ぐため、組織全体で情報管理体制を見直す必要があります。
- 退職時のデータチェックリストを策定・運用。
- アクセス権限の一元管理と定期的見直しを実施。
- 機密情報の監視・ログ分析を強化。
退職時のデータ削除はフォレンジック調査会社に依頼する

適切な調査によって原因究明を行うためにも、フォレンジック調査の専門家に相談することが重要です。特に、法的手続きが絡むケースや被害が広範囲に及ぶ場合は、専門家の力を借りることで被害の最小化と信頼性の高い証拠の収集が可能です。
当社では、インシデント対応のプロが初動対応から、専門設備でのネットワークや端末の調査・解析、調査報告書の提出、ならびに報告会によって問題の解決を徹底サポートします。
フォレンジックサービスの流れや料金については下記からご確認ください。
【初めての方へ】フォレンジックサービスについて詳しくご紹介
【サービスの流れ】どこまで無料? 調査にかかる期間は? サービスの流れをご紹介
【料金について】調査にかかる費用やお支払方法について
【会社概要】当社へのアクセス情報や機器のお預かりについて
デジタルデータフォレンジックの強み
デジタルデータフォレンジックは、迅速な対応と確実な証拠収集で、お客様の安全と安心を支える専門業者です。デジタルデータフォレンジックの強みをご紹介します。
累計相談件数47,431件以上のご相談実績
官公庁・上場企業・大手保険会社・法律事務所・監査法人等から個人様まで幅広い支持をいただいており、累積47,431件以上(※1)のご相談実績があります。また、警察・捜査機関から累計409件以上(※2)のご相談実績があり、多数の感謝状をいただいています。
(※1)集計期間:2016年9月1日~
(※2)集計機関:2017年8月1日~
国内最大規模の最新設備・技術
自社内に40名以上の専門エンジニアが在籍し、17年連続国内売上No.1のデータ復旧技術(※3)とフォレンジック技術でお客様の問題解決をサポートできます。多種多様な調査依頼にお応えするため、世界各国から最新鋭の調査・解析ツールや復旧設備を導入しています。
(※3)第三者機関による、データ復旧サービスでの売上の調査結果に基づく。(2007年~2023年)
24時間365日スピード対応
緊急性の高いインシデントにもいち早く対応できるよう24時間365日受付しております。
ご相談から最短30分で初動対応のWeb打合せを開催・即日現地駆けつけの対応も可能です。(法人様限定)自社内に調査ラボを持つからこそ提供できる迅速な対応を多数のお客様にご評価いただいています。
デジタルデータフォレンジックでは、相談から初期診断・お見積りまで24時間365日体制で無料でご案内しています。今すぐ専門のアドバイザーへ相談することをおすすめします。
\匿名相談OK・ご相談前にNDA締結可能/
企業が取るべき具体的対策
退職時のデータ削除リスクに備えるためには、事前の制度設計と技術的・人的な対策が不可欠です。
機密情報の運用ルール整備
退職時のトラブルを未然に防ぐには、入社時から「情報資産の取扱規定」を明文化し、研修や社内マニュアルで周知することが重要です。
- 社内規程に「業務データは会社の資産」と明記する。
- 退職時に改めて説明し、誓約書にサインさせる。
- 共有ドライブやPCの私的使用禁止を徹底する。
アカウント停止の即時実行
退職者のアカウントをいつまでも有効のままにしておくと、不正アクセスや削除行為を許すことになります。
- 退職当日、業務終了時刻と同時にアカウントを無効化。
- 二要素認証の解除、VPNアクセスの遮断も同時に行う。
- パスワード変更履歴の確認とアーカイブも実施。
退職直前のログ監査
退職前の1~2週間は、ファイル操作ログやUSB接続履歴、クラウドストレージアクセス履歴を監査することが推奨されます。
- ログ取得ツール(SIEMやEDR)で操作履歴を収集。
- 異常操作(大量削除、夜間アクセスなど)を抽出。
- 問題がある場合は退職手続き前にヒアリングを実施。
退職前の端末チェック
PC・スマホ・外付けHDDなどの端末に異常がないかを確認し、個人データの削除や業務データの持ち出しを防ぎます。
- Finderやエクスプローラーでゴミ箱や隠しフォルダを確認。
- クラウドストレージの同期状況を調べる。
- 必要に応じてフォレンジック調査を依頼。
個人情報漏洩への対応フロー
削除されたデータに個人情報が含まれていた場合、「個人情報保護法」に基づき、関係省庁や顧客への報告義務が発生します。
- 削除されたファイル内容を復元・調査する。
- 個人情報が確認された場合は、漏洩件数を特定。
- 速やかに関係機関(個人情報保護委員会)に報告。
まとめ|退職時のデータ削除は慎重に
退職時のデータ削除は、企業にとっても従業員にとっても大きなリスクを伴います。企業側は予防策として制度・監査体制を構築し、従業員はルールを理解したうえで、適切な情報管理を心掛ける必要があります。
無断削除は懲戒・損害賠償・刑事訴追のリスクを伴う行為です。円満な退職を迎えるためにも、事前の準備と誠実な対応を徹底しましょう。
\匿名相談に対応 法人様はWeb打ち合わせも可能/
よくある質問
対応内容・期間などにより変動いたします。
詳細なお見積もりについてはお気軽にお問い合わせください。
専門のアドバイザーがお客様の状況を伺い、概算の見積りと納期をお伝えいたします。
可能です。当社は特定の休業日はございません。緊急度の高い場合も迅速に対応できるように、365日年中無休で対応いたしますので、土日祝日でもご相談下さい。
もちろん可能です。お客様の重要なデータをお取り扱いするにあたり、当社では機密保持誓約書ををお渡しし、機器やデータの取り扱いについても徹底管理を行っております。また当社では、プライバシーの保護を最優先に考えており、情報セキュリティの国際規格(ISO24001)およびPマークも取得しています。法人様、個人様に関わらず、匿名での相談も受け付けておりますので、安心してご相談ください。