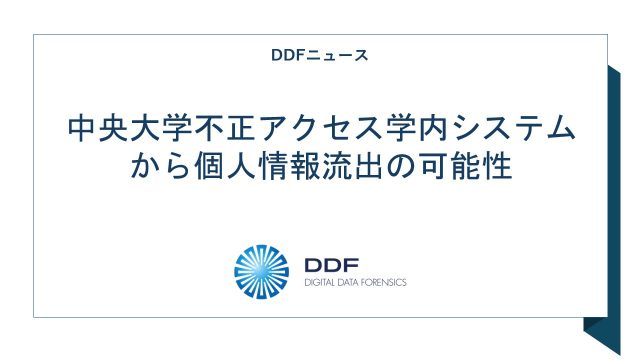サイバー攻撃や社内不正によって、情報やシステムが脅かされる「セキュリティインシデント」が年々増加しています。被害内容は単なるトラブルにとどまらず、社会的信用の失墜や法的リスクにまで発展するケースも少なくありません。
とはいえ、インシデントの定義が曖昧なままでは、初動対応や再発防止の優先順位が見えづらくなります。放置すれば適切な対応を行うための痕跡が消失する恐れもあるため、正しい知識と判断軸を持つことが重要です。
本記事では、セキュリティインシデントの基本的な定義、発生原因、想定される被害内容、対処法、予防策について紹介します。
\24時間365日 無料相談受付中/
目次
セキュリティインシデントとは
セキュリティインシデントとは、企業や組織の情報セキュリティを脅かす「望ましくない事象」全般を指します。ISO 27000シリーズの定義では、「業務や情報セキュリティを脅かす、望まないまたは予期しない情報セキュリティ事象」とされており、実際の被害内容が発生していなくても、脅威の兆候だけでインシデントと見なされることがあります。
たとえば、マルウェアの侵入、不正アクセス、情報漏えい、システム障害、内部不正などが該当します。また、天災による障害や設備トラブルも含まれる場合があるなど、その範囲は非常に広範です。
重要なのは、インシデントの早期検知と迅速な初動対応によって、被害内容の拡大や信用の喪失を未然に防ぐことです。そのためには、平時からのルール整備や教育、そして万が一に備えた対応フローの設計が不可欠です。
セキュリティインシデントが起きる原因
セキュリティインシデントの原因は、外部からの攻撃だけでなく、内部のミスや管理不備、自然災害など多岐にわたります。以下では、代表的な発生要因を4つの視点で紹介します。
外部攻撃(マルウェアや不正アクセス)
マルウェア感染や標的型攻撃、不正アクセスなど、外部からの侵入によるインシデントは、セキュリティインシデントの代表的な要因です。特に脆弱なシステムや認証の甘さを突かれると、内部情報が漏えいしたり、業務が妨害されたりする恐れがあります。
内部ミス・ヒューマンエラー
誤送信や設定ミス、パスワードの使い回しといった人為的なミスも、セキュリティインシデントの大きな原因です。ITリテラシーの不足や教育の不徹底が背景にあることが多く、組織としての再発防止策が必要です。
管理体制・組織の不備
CSIRT(インシデント対応チーム)の未整備、ルールの形骸化、教育の不徹底など、組織全体のセキュリティ文化の欠如が原因となるケースも少なくありません。属人化した管理体制では、リスクの早期発見や対応が難しくなります。
自然災害・物理的なトラブル
地震や台風、停電、サーバルームの温度異常など、物理的なトラブルによってもインシデントは発生します。クラウドサービスの障害やバックアップの不備が被害の拡大につながる場合もあるため、BCP(事業継続計画)の観点からも対策が重要です。
以上がセキュリティインシデントの原因です。最悪の場合、個人情報の漏えいや長期間の業務停止など大規模なインシデントに被害が拡大する可能性もあるため、早めに専門家を交えた対応が必要です。
デジタルデータフォレンジックなら、セキュリティインシデントの相談を24時間365日受け付けております。
法人のお客様には、最短15分以内でのWeb面談にも対応しており、ランサムウェア被害や情報持ち出しなどの重大なセキュリティインシデントに対して、迅速に調査体制を構築することが可能です。
\24時間365日 無料相談受付中/
セキュリティインシデントの主な被害内容
セキュリティインシデントが発生すると、単なる一時的なトラブルにとどまらず、経済的損失や業務の停止、社会的信用の低下、さらには法的責任まで波及する可能性があります。特に法人においては、取引先や顧客、株主への説明責任も問われるため、被害内容を把握しておくことが重要です。
金銭的な損失
インシデント対応や復旧にかかる直接費用のほか、営業損失、顧客離脱による長期的な損害が発生することもあります。罰金や賠償、再発防止にかかる投資も含めると、実害は想定よりも大きくなる傾向にあります。
業務・運営への影響
サービス停止や業務中断は、顧客対応や納期に支障をきたします。サーバのダウンやメール不達が続くと、社内外に混乱を招き、復旧後もしばらく影響が残るケースが多く見られます。
社会的信用の低下
情報漏えいや対応の不備は、取引先・顧客・株主などステークホルダーからの信頼を損なう可能性があります。報道やSNSで拡散された場合には、風評被害が長期的に残ることもあります。
法的手続きの必要性に迫られる
個人情報や機密情報が関係する場合、個人情報保護法や業界規制に基づく対応が求められます。行政への報告、公表義務、訴訟リスクなど、法的な手続きとコストが発生します。
不審なアクセスや業務端末の異常が続き、どこまで被害が及んでいるのか判断に迷う場面もあるかもしれません。
自己対応を優先すると適切な対応を行うための痕跡が消失する恐れがあり、原因の特定や再発防止の根拠を欠いた対応になってしまう可能性があります。
当社では、セキュリティインシデントの発生経緯や操作ログを時系列で整理し、侵入経路・影響範囲・外部送信の有無を明らかにする調査を行います。官公庁・上場企業を含む39,451件以上(期間:2016年9月以降)の相談実績があり、24時間365日相談を受け付けています。
\24時間365日 無料相談受付中/
セキュリティインシデントが発生した時の対処法
インシデント発生時は、慌てず冷静に、被害の拡大を防ぎつつ、原因と範囲を明らかにするための対応が必要です。以下を参考にしてください。
安全確認と隔離
異常が確認された端末やシステムは、まずネットワークから切り離し、拡大を防ぐ必要があります。電源断などの操作は証拠を破壊する可能性があるため、注意が必要です。
- 影響範囲の資産をネットワークから一時切断する
- 対象端末の電源断を避け、状態を維持する
- 社内関係者に状況を共有し、体制を整える
証拠保全
証拠となるログやファイルは、時間の経過とともに上書きや削除のリスクが高まります。正しい手順での保全により、後の調査の信頼性が担保されます。
- ログ・ファイル・設定を取得し、タイムスタンプを記録する
- ハッシュ値を取り、改ざんがない状態で保管する
- 保全媒体と取得者・日時・操作内容を記録する
影響範囲の把握
誰が、いつ、どのシステムに何をしたのかを明らかにすることで、適切な対処と再発防止に繋がります。端末・アカウント・データ単位で時系列を整理することが重要です。
- 不審なアクセス・操作履歴を洗い出す
- 各端末・サービスの利用ログを時系列で整理する
- 被害データとその関連資産を特定し、対応対象を決定する
フォレンジック調査会社に相談する
セキュリティインシデントが発生した際、被害の正確な把握や再発防止のためには、専門的な技術に基づいた調査が不可欠です。特に、ランサムウェア感染や情報の持ち出し、不正アクセスなどの重大なインシデントでは、初動を誤ることで証拠が消失し、原因の特定や法的対応が困難になるケースが多く報告されています。
こうした事態に備え、フォレンジック調査会社(※デジタル機器内の証拠を解析・保全する専門機関)への早期相談が効果的です。
- 不正アクセスやマルウェアの侵入経路・実行履歴の特定
- ハードディスクやクラウド上のログ・ファイル操作履歴の保全と解析
- 証拠保全に基づいた調査レポートの作成(社内報告・法的手続き対応に活用可能)
- 複数端末・クラウド・メールサーバ等にまたがる包括的な影響範囲の把握
また、調査中の再感染リスクの抑制や、社内CSIRTや経営層との情報共有支援も行ってくれるため、インシデント対応に不慣れな組織でも安心して任せることができます。
特に法人の場合、調査スピードが経営判断や取引継続に直結するため、「異常かもしれない」と感じた時点で即時に相談する判断力が求められます。
初動対応に迷うよりも、まずは専門家に状況を伝え、証拠が残っているうちに技術的な判断を仰ぐことが、被害最小化への最短ルートです。
\24時間365日 無料相談受付中/
詳しく調べる際はフォレンジック調査会社に相談を
 サイバー攻撃、不正アクセス、マルウェア感染のような問題が発生した場合、どのような経路で、どのような情報が漏えいしたのか、被害の全容を正確に把握する必要があります。適切な調査によって原因究明を行うためにも、フォレンジック調査の専門家に相談することが重要です。
サイバー攻撃、不正アクセス、マルウェア感染のような問題が発生した場合、どのような経路で、どのような情報が漏えいしたのか、被害の全容を正確に把握する必要があります。適切な調査によって原因究明を行うためにも、フォレンジック調査の専門家に相談することが重要です。
特に、法的手続きが絡むケースや被害が広範囲に及ぶ場合は、専門家の力を借りることで被害の最小化と信頼性の高い証拠の収集が可能です。
>情報漏えい時の個人情報保護委員会への報告義務とは?詳しく解説
当社では、インシデント対応のプロが初動対応から、専門設備でのネットワークや端末の調査・解析、調査報告書の提出、ならびに報告会によって問題の解決を徹底サポートします。
フォレンジックサービスの流れや料金については下記からご確認ください。
【初めての方へ】フォレンジックサービスについて詳しくご紹介
【サービスの流れ】どこまで無料? 調査にかかる期間は? サービスの流れをご紹介
【料金について】調査にかかる費用やお支払方法について
【会社概要】当社へのアクセス情報や機器のお預かりについて
デジタルデータフォレンジックの強み
デジタルデータフォレンジックは、迅速な対応と確実な証拠収集で、お客様の安全と安心を支える専門業者です。デジタルデータフォレンジックの強みをご紹介します。
累計相談件数47,431件以上のご相談実績
官公庁・上場企業・大手保険会社・法律事務所・監査法人等から個人様まで幅広い支持をいただいており、累積47,431件以上(※1)のご相談実績があります。また、警察・捜査機関から累計409件以上(※2)のご相談実績があり、多数の感謝状をいただいています。
(※1)集計期間:2016年9月1日~
(※2)集計機関:2017年8月1日~
国内最大規模の最新設備・技術
自社内に40名以上の専門エンジニアが在籍し、17年連続国内売上No.1のデータ復旧技術(※3)とフォレンジック技術でお客様の問題解決をサポートできます。多種多様な調査依頼にお応えするため、世界各国から最新鋭の調査・解析ツールや復旧設備を導入しています。
(※3)第三者機関による、データ復旧サービスでの売上の調査結果に基づく。(2007年~2023年)
24時間365日スピード対応
緊急性の高いインシデントにもいち早く対応できるよう24時間365日受付しております。
ご相談から最短30分で初動対応のWeb打合せを開催・即日現地駆けつけの対応も可能です。(法人様限定)自社内に調査ラボを持つからこそ提供できる迅速な対応を多数のお客様にご評価いただいています。
デジタルデータフォレンジックでは、相談から初期診断・お見積りまで24時間365日体制で無料でご案内しています。今すぐ専門のアドバイザーへ相談することをおすすめします。
調査の料金・目安について
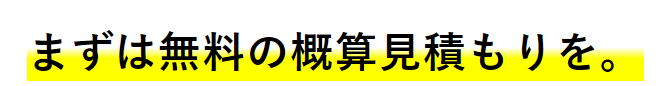 専門のアドバイザーがお客様の状況を伺い、概算の見積りと納期をお伝えいたします。
専門のアドバイザーがお客様の状況を伺い、概算の見積りと納期をお伝えいたします。
機器を来社お持込み、またはご発送頂ければ、無料で正確な見積りのご提出が可能です。
まずはお気軽にお電話下さい。
【法人様限定】初動対応無料(Web打ち合わせ・電話ヒアリング・現地保全)
❶無料で迅速初動対応
お電話でのご相談、Web打ち合わせ、現地への駆け付け対応を無料で行います(保全は最短2時間で対応可能です。)。
❷いつでも相談できる
365日相談・調査対応しており、危機対応の経験豊富なコンサルタントが常駐しています。
❸お電話一本で駆け付け可能
緊急の現地調査が必要な場合も、調査専門の技術員が迅速に駆け付けます。(駆け付け場所によっては出張費をいただく場合があります)
セキュリティインシデントを未然に防ぐための対策
セキュリティインシデントは、一度でも発生すると組織へのダメージが大きく、完全な復旧には多大な時間とコストがかかります。だからこそ、日常的な管理体制や教育、技術的対策によって、事前に防ぐ姿勢が重要です。ここでは、予防の基本となる3つの対策を紹介します。
セキュリティポリシーの策定と周知
企業として情報資産をどう扱うかをルール化し、組織全体で遵守する仕組みが不可欠です。書面だけでなく、現場で守られているかの運用レベルまで徹底することが重要です。
- 情報資産の種類と取り扱いルールを明文化する
- 全従業員への共有と受講履歴の管理を行う
- 定期的な監査と改善サイクルを設ける
アクセス管理と認証強化
情報資産へのアクセスは、必要な人に必要な範囲だけ許可する原則が重要です。また、パスワードの管理や多要素認証(MFA)の導入は、不正アクセスの防止に非常に効果的です。
- 役割ごとに最小限のアクセス権限を設計する
- MFAを導入し、ID・パスワード単独認証を避ける
- 退職者や異動時に速やかにアカウントを停止する
従業員へのセキュリティ教育
ヒューマンエラーによる情報漏えいやマルウェア感染を防ぐため、日常的な教育と訓練が必要です。形式的な座学ではなく、実例を交えた内容や反復による定着が重要です。
- フィッシング詐欺や標的型攻撃の事例を教材にする
- eラーニングや演習形式で体験的に学ぶ
- 年1回以上の受講と理解度テストを義務化する
よくある質問
対応内容・期間などにより変動いたします。
詳細なお見積もりについてはお気軽にお問い合わせください。
専門のアドバイザーがお客様の状況を伺い、概算の見積りと納期をお伝えいたします。
可能です。当社は特定の休業日はございません。緊急度の高い場合も迅速に対応できるように、365日年中無休で対応いたしますので、土日祝日でもご相談下さい。
もちろん可能です。お客様の重要なデータをお取り扱いするにあたり、当社では機密保持誓約書ををお渡しし、機器やデータの取り扱いについても徹底管理を行っております。また当社では、プライバシーの保護を最優先に考えており、情報セキュリティの国際規格(ISO24001)およびPマークも取得しています。法人様、個人様に関わらず、匿名での相談も受け付けておりますので、安心してご相談ください。