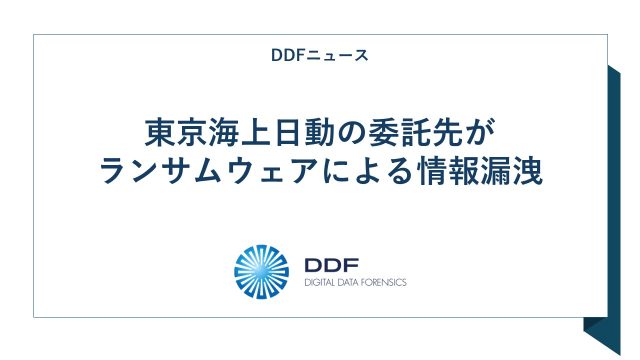パスワードの漏洩や社内情報の流出は、技術的な問題だけでなく、人の心理や行動を悪用する攻撃によって発生する場合があります。ソーシャルエンジニアリングは、システムではなく人を標的にした手法であり、企業にとって見落としがちなリスクの一つです。
この記事では、ソーシャルエンジニアリングの主な手口、実際の被害事例、企業として取り組むべき対策について、分かりやすくまとめています。
この記事を書いた人
目次
ソーシャルエンジニアリングとは
ソーシャルエンジニアリングとは、システムやソフトウェアの脆弱性を狙うのではなく、人間の心理や行動の隙を突いて、情報を不正に取得する攻撃手法です。
攻撃者は、対象となる人物の信頼を得たり、焦りや不安を利用したりすることで、パスワード・個人情報・業務データなどを「自発的に提供させる」状況を作り出します。こうした手法は、技術的なセキュリティ対策では見落とされやすく、発覚も遅れるため、情報漏えいや金銭被害につながるリスクが非常に高いとされています。
たとえば、サポート窓口を装って電話でパスワードを聞き出す、取引先になりすましてメールを送る、廃棄された紙資料から機密情報を拾い上げるなど、一見すると無害に思える行動を通じて攻撃が行われます。
ソーシャルエンジニアリングの手口
ソーシャルエンジニアリングの攻撃は、心理的な油断や信頼を利用して、情報を盗み取る点が特徴です。直接的な技術攻撃ではなく、人を狙う手法のため、気づきにくく被害が広がりやすい傾向があります。
以下に代表的な手口と特徴をまとめています。
なりすまし(メール・電話・チャットなど)
社内の上司や取引先、別部署の担当者などになりすまし、電話やメール、チャットを使って機密情報を引き出す手口です。攻撃者は口調や署名、文面の癖まで模倣し、対象者の信頼を獲得したうえで、IDやパスワードを聞き出します。
最近では、TeamsやSlack、LinkedInなどのビジネス向けSNSやチャットツールを活用したなりすましも増加傾向にあります。
https://digitaldata-forensics.com/column/cyber_security/17722/
フィッシング
銀行や有名企業のロゴ・文面をコピーした偽のメールを送り、専用の偽サイトに誘導し、ログイン情報やカード情報などを入力させて盗み出す詐欺です。
メールだけでなく、SMS(ショートメッセージ)やSNSのDM経由でもフィッシングが行われ、モバイル利用者を標的とした手口が拡大しています。

BEC(ビジネスメール詐欺)
経営層や海外の取引先を装い、経理部門や財務担当者に対して偽の送金依頼を送る手口です。送金指示が本物に見えるよう、実際の業務メールのやり取りを分析・模倣して送信されることが特徴です。
国内でも数千万円~数億円単位の被害が発生しており、企業の財務リスクとして極めて深刻な問題です。

プレテキスティング
IT管理者やサポート窓口、調査員、外部業者などの「信頼されやすい立場」を偽り、正当な業務を装って接触し、機密情報を聞き出す詐欺です。
本人確認手順が曖昧な組織では、簡単に情報が漏れるリスクが高く、役職者や新人が標的にされることもあります。
Vishing(電話を使った詐欺)
電話を使ったフィッシング手法で、銀行や公的機関、サービスのカスタマーセンターを装い、暗証番号やワンタイムパスワードを電話越しに聞き出します。
自動音声を使った偽の案内で信用させるケースも多く、実際に警察や金融機関を名乗る手口も確認されています。
SNS/OSINTを使った信用構築型詐欺
SNSの投稿や会社のWebサイト、登記情報、IR資料など、誰でも見られる情報(OSINT)をもとに、相手の興味や人間関係、業務内容を分析して接触し、信頼を築いたうえで情報を引き出す手法です。
この手口は特定の人物を狙う「標的型攻撃(スピアフィッシング)」と組み合わせて使われ、外部からは見抜きにくい高度な詐欺となっています。

ソーシャルエンジニアリングによる被害は、外部からの攻撃と違って明確な痕跡が残りにくく、表面化した時点ではすでにパスワードの漏洩や個人情報の流出、不正送金など、深刻な被害が進行している可能性があります。
不審なメールを開いた覚えがある方や、正体があいまいな相手とやり取りをした記憶がある場合は、すでに情報が狙われている恐れも否定できません。
重大な被害を未然に防ぐためには、早い段階で専門調査機関へ相談することが極めて重要です。
ソーシャルエンジニアリングが企業にもたらす被害
人を標的にしたソーシャルエンジニアリングは、侵入の発見が遅れやすく、企業の事業継続に多方面から深刻な影響を与える可能性があります。情報漏えい・金銭的被害・信頼の失墜といった結果を招きやすいため、早期のリスク把握と対策が重要です。
以下によくある被害を解説します。
企業の信用失墜・ブランド毀損
情報漏えいや不正送金の発生は、報道やSNSによって瞬時に広がり、企業の社会的信用に直接的な打撃を与えます。顧客や取引先からの信頼を失うだけでなく、株価や新規契約にも影響が及び、事業運営全体に悪影響を及ぼす恐れがあります。
法的責任・訴訟リスク
個人情報や機密情報の漏えいが発生した場合、関連法令に基づく行政処分や監督官庁からの調査対象となることがあります。また、被害を受けた顧客・取引先から損害賠償を求められるケースも想定され、法的対応の負担は小さくありません。

機密情報・個人情報の漏えい
IDやパスワード、製品開発情報、顧客データなどが外部に流出すると、競争優位性の喪失や信頼性の低下を招きます。ひとたび外部に拡散すれば、完全な回収は困難であり、情報管理体制そのものの見直しが必要となる場合もあります。

金銭的損失
不正送金や詐欺によって直接的な金銭被害が発生するケースは後を絶ちません。加えて、被害後に必要となる外部調査や法的対応、再発防止の仕組みづくりなどにも多大なコストが発生し、経営資源を圧迫する結果につながります。
業務の中断・遅延
攻撃によるシステム障害や社内対応の混乱が発生した場合、日常業務の進行が大きく阻害されます。顧客対応や納品スケジュールにも影響し、最終的にはサービス品質の低下や取引機会の損失に直結します。
ソーシャルエンジニアリングによる被害は、水面下で進行しやすく、発覚した時点ではすでに被害が広がっている場合もあります。社内だけでの対応には限界があり、誤った初動判断がさらなる二次被害を招くおそれもあります。
情報流出や不正アクセスの可能性を少しでも感じた段階で、早めに専門調査会社に相談することが最も重要です。
ソーシャルエンジニアリングの実際の被害事例
ソーシャルエンジニアリングによる攻撃は、実際の企業や著名人アカウントにも深刻な被害を与えています。代表的な2つの事例を紹介します。
ストレージ王 不正送金事件(2024年)
上場企業「ストレージ王」が、金融機関のオペレーターを装った第三者の指示に従ったことで、インターネットバンキングの認証情報を盗まれ、7,600万円を不正送金される被害が発生しました。
この事件では、金融機関を装った巧妙ななりすまし連絡によって、経理担当者が標的となり、ソーシャルエンジニアリングの脅威が現実化した典型例とされています。
Twitter著名人アカウント乗っ取り事件(2020年)
2020年、Twitterでビル・ゲイツ氏やオバマ元大統領など著名人のアカウントが一斉に乗っ取られ、ビットコイン詐欺ツイートが発信される事件が起きました。乗っ取りはTwitter社内のIT権限を狙ったスピアフィッシングにより実行されました。
被害は12.86BTCの不正送金に加え、DMの閲覧やアカウント情報の流出にも及びました。社内権限を悪用した内部侵害の危険性と、情報管理体制の重要性が浮き彫りになった事例です。
出典:日経クロステック
情報漏えいが発生した時専門の調査会社に相談
ソーシャルエンジニアリングによる情報漏えいは、人の判断や組織の手続きの隙を突くため、被害範囲の特定が難しくなりがちです。技術的な対策だけでは対応しきれない場面も多く、専門の調査会社による総合的な分析が効果的です。
ソーシャルエンジニアリング特有の調査ポイント
ソーシャルエンジニアリングの攻撃には、次のような視点での調査が必要です。
- 情報収集や標的設定の経緯: 公開情報やSNSなど、どのような経路で標的にされたかを把握します。
- 人的セキュリティ運用: 社員教育、本人確認手続き、来訪者管理などの実施状況を確認します。
- 初動対応と記録体制: インシデント発生時の対応記録やエスカレーションの仕組みを確認します。
- アクセス履歴や操作ログ: 社内システムやデバイスの利用履歴から、不審な挙動を検出します。
- 外部委託や運用フロー: 業務委託先の管理体制や、運用ルールの遵守状況を調査します。
上記観点を総合的に確認することで、原因の特定だけでなく、今後の再発防止にもつながります。
フォレンジック調査の有効性
情報がどこまで漏れているかを確認したい場合や、不正アクセスやマルウェア感染の疑いがある場合には、フォレンジック調査が効果的です。
フォレンジック調査(デジタルフォレンジック調査)とは、PCやスマホの内部ログを解析し、不正アクセスやマルウェア感染の有無を調べる技術です。警察の捜査でも活用される高度な手法で、個人情報漏えいの可能性や被害範囲の特定に役立ちます。
さらに、以下の内容も調査することが可能です。
- 不正アクセスがどの経路から行われたか(例:リモート操作、遠隔ソフト)
- どのファイル・データが外部に送信された可能性があるか
- マルウェアやスパイウェアの感染履歴・痕跡の有無
- 個人情報(氏名・住所・パスワード・カード情報など)の漏えいリスクの程度
さまざまなリスクが考えられるため、一度フォレンジック調査会社など専門家に相談することが推奨されます。
>フォレンジック調査とは?メリットやインシデント別の調査事例を解説
当社では、デジタルフォレンジックの技術を用いて、情報漏えいの有無を調べるサービスをご用意しています。24時間365日ご相談を受付けており、専門アドバイザーによる相談から見積りまで無料でご案内していますので、自己判断では不安な場合はお気軽にご相談ください。
自力で対応できない場合はフォレンジック調査の専門業者に依頼する
 ハッキングや不正アクセス、ウイルス感染、情報漏えいなどの問題が起きた際、自分だけでの対応が難しいと感じたら、迷わずフォレンジック調査の専門業者に相談しましょう。
ハッキングや不正アクセス、ウイルス感染、情報漏えいなどの問題が起きた際、自分だけでの対応が難しいと感じたら、迷わずフォレンジック調査の専門業者に相談しましょう。
どこから侵入され、どんな情報が漏れたのかを正しく把握することが重要です。特に、被害が大きい場合や情報が悪用された疑いがある場合は、専門家によるフォレンジック調査を実施することで、被害の拡大を未然に防ぐ有効な対策につながります。
信頼できる業者を選び、早めに動くことが、トラブルを最小限に抑えるポイントです。
フォレンジックサービスの流れや料金については下記からご確認ください。
【初めての方へ】フォレンジックサービスについて詳しくご紹介
【サービスの流れ】どこまで無料? 調査にかかる期間は? サービスの流れをご紹介
【料金について】調査にかかる費用やお支払方法について
【会社概要】当社へのアクセス情報や機器のお預かりについて
デジタルデータフォレンジックの強み
デジタルデータフォレンジックは、迅速な対応と確実な証拠収集で、お客様の安全と安心を支える専門業者です。デジタルデータフォレンジックの強みをご紹介します。
累計相談件数47,431件以上のご相談実績
官公庁・上場企業・大手保険会社・法律事務所・監査法人等から個人様まで幅広い支持をいただいており、累積47,431件以上(※1)のご相談実績があります。また、警察・捜査機関から累計409件以上(※2)のご相談実績があり、多数の感謝状をいただいています。
(※1)集計期間:2016年9月1日~
(※2)集計機関:2017年8月1日~
国内最大規模の最新設備・技術
自社内に40名以上の専門エンジニアが在籍し、17年連続国内売上No.1のデータ復旧技術(※3)とフォレンジック技術でお客様の問題解決をサポートできます。多種多様な調査依頼にお応えするため、世界各国から最新鋭の調査・解析ツールや復旧設備を導入しています。
(※3)第三者機関による、データ復旧サービスでの売上の調査結果に基づく。(2007年~2023年)
24時間365日スピード対応
緊急性の高いインシデントにもいち早く対応できるよう24時間365日受付しております。
ご相談から最短30分で初動対応のWeb打合せを開催・即日現地駆けつけの対応も可能です。(法人様限定)自社内に調査ラボを持つからこそ提供できる迅速な対応を多数のお客様にご評価いただいています。
デジタルデータフォレンジックでは、相談から初期診断・お見積りまで24時間365日体制で無料でご案内しています。今すぐ専門のアドバイザーへ相談することをおすすめします。
ソーシャルエンジニアリング攻撃への日常対策
情報を守るためには、技術だけでなく日々の行動や組織の意識づけも欠かせません。以下に、実践すべき日常対策を整理しています。
1. 基本的な心構えと行動
攻撃の多くは人の油断や思い込みにつけ込むものです。常に「不審な点はないか」という警戒心を持ち、情報を扱う際にはその重要性を認識したうえで慎重な対応を心がける必要があります。
- 不審な連絡に即答せず、一度立ち止まって確認する
- 情報は資産と認識し、他人に簡単に話さない
- 本人確認を徹底し、信頼できるルート以外ではやり取りしない
2. 技術的・物理的な対策
システム面とオフィス環境の両方での対策が求められます。基本的なセキュリティ設定だけでなく、入退室や端末管理など日常の物理的な管理も重要です。
- 多要素認証(MFA)の導入
- 強固なパスワードと定期変更の実施
- セキュリティソフト・OSのアップデート
- 画面ロック、入退室管理の徹底
3. 日常業務での注意点
業務の中には、攻撃者にとって絶好の“すき”が潜んでいます。メール・資料管理・SNS活用など、日々の対応を見直すことが被害予防につながります。
- 不審なメールや添付ファイルは開かない
- USBや記憶媒体は必ず確認してから接続
- 紙資料は施錠・廃棄処理を徹底
- SNS投稿前に内容と範囲を再確認
4. 教育・組織的な取り組み
個人の意識だけでは限界があります。組織全体でのセキュリティ文化を育て、仕組みとして定着させる取り組みが不可欠です。
- 定期的なセキュリティ教育・模擬訓練
- セキュリティポリシーと運用ルールの明文化
- インシデント対応手順の整備と共有
どれだけ技術的な対策を講じても、最終的に狙われるのは「人の判断」や「日常の行動」です。日々の業務に潜む小さな油断が、重大な情報漏えいにつながる恐れがあります。
最も効果的な防御は、個人と組織がともに危機意識を持ち、対策を継続することです。一人ひとりの意識と行動の積み重ねが、組織全体のリスクを大きく下げる力になります。
まとめ
ソーシャルエンジニアリングは、人の心理や日常業務の油断を突く見えにくい脅威です。企業にとっては、信頼や事業継続に深刻な影響を及ぼすリスクとなります。技術対策に加え、日々の行動や仕組みの見直しが不可欠です。情報漏えいが疑われる場合は、早期に専門調査機関へ相談することが被害拡大の防止につながります。
よくある質問
対応内容・期間などにより変動いたします。
詳細なお見積もりについてはお気軽にお問い合わせください。
専門のアドバイザーがお客様の状況を伺い、概算の見積りと納期をお伝えいたします。
可能です。当社は特定の休業日はございません。緊急度の高い場合も迅速に対応できるように、365日年中無休で対応いたしますので、土日祝日でもご相談下さい。
もちろん可能です。お客様の重要なデータをお取り扱いするにあたり、当社では機密保持誓約書ををお渡しし、機器やデータの取り扱いについても徹底管理を行っております。また当社では、プライバシーの保護を最優先に考えており、情報セキュリティの国際規格(ISO24001)およびPマークも取得しています。法人様、個人様に関わらず、匿名での相談も受け付けておりますので、安心してご相談ください。