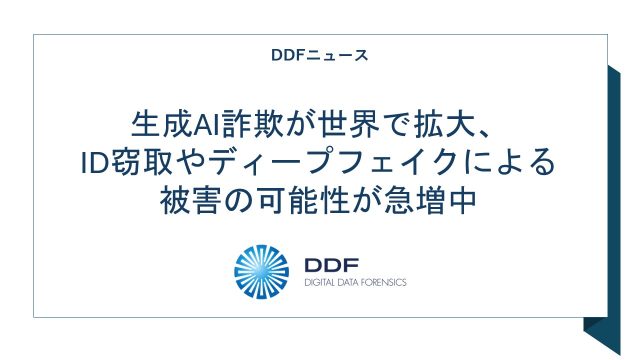テレワークの普及により、柔軟な働き方が可能になった一方で、情報漏洩のリスクも増加しています。社外で業務を行う環境では、従来のオフィス内で仕事をすることと比較して、セキュリティの管理が難しくなり、不注意や設定ミス、さらには内部不正が原因で機密情報が流出するケースも少なくありません。
流出した機密情報の内容によっては、不正アクセスなどのサイバー攻撃や、競合他社に技術が漏洩し、模倣されるといった重大なリスクに発展するおそれもあります。
本記事では、テレワークに伴う情報漏洩の代表的な原因と、万一漏洩が疑われた場合の対処法、そして事前に講じておくべき予防策について詳しく解説します。
ご相談は匿名でも可能です。機密情報を含む場合も、事前にNDA(秘密保持契約)を締結してからの対応も可能ですので、まずは専用窓口までご連絡ください。
テレワークで情報漏洩が発生する主な原因
テレワークで情報漏洩が発生する主な原因は以下の通りです。
端末の紛失・盗難
自宅以外の場所で業務を行う際、ノートPCやスマートフォンなどの業務用端末を持ち歩く機会が増えます。その結果、カフェや公共交通機関での置き忘れや盗難が発生しやすくなります。
端末にパスワードや暗号化が設定されていない場合、保存されている顧客情報や社内資料が外部に流出するリスクがあります。テレワークでは、端末管理の徹底と紛失時の迅速な遠隔ロック・初期化体制が不可欠です。
公共Wi-Fiや自宅ネットワークの脆弱性
カフェや駅などの公共Wi-Fiは暗号化が甘く、通信内容を盗み見られる危険があります。また、自宅ネットワークでも初期設定のまま使用していると、不正アクセスのリスクが高まります。
攻撃者に通信経路を傍受された場合、ID・パスワードや業務データが漏洩する可能性があります。VPNやWPA3対応ルーターの導入、SSIDやパスワードの適切な設定が求められます。
誤送信・誤操作
テレワークでは対面での確認が難しいため、資料やメールを誤って送信してしまうヒューマンエラーが起こりがちです。特に社外へのメール送信時、ファイルの添付ミスや送信先アドレスの選択ミスによって、機密情報が意図せず外部に流出する事例が多発しています。
送信前の複数確認や、送信内容を一定時間保留するシステムの導入などが有効な対策です。
クラウドサービスの設定不備
Google DriveやDropboxなどのクラウドサービスは、利便性が高い反面、設定ミスによる情報漏洩が多発しています。たとえば、共有設定を「リンクを知っていれば誰でも閲覧可」に設定していると、意図しない第三者に情報が閲覧されるリスクがあります。
端末ののぞき見
外出先で作業をする際、周囲の人に画面をのぞき見されてしまう「ショルダーハッキング」が発生することがあります。重要な業務内容や顧客情報が第三者に見られることで、情報漏洩につながるおそれがあります。
のぞき見防止フィルターの装着や、機密性の高い業務を公共の場で行わないなど、物理的なセキュリティ意識も必要です。
サイバー攻撃
テレワーク環境下では、オフィスと比較してセキュリティ体制が脆弱なことが多く、マルウェア感染やフィッシング攻撃、不正アクセス等のサイバー攻撃リスクが高まります。特にVPNを狙った攻撃や、偽の業務メールによる認証情報の窃取は深刻です。
情報漏洩が関係するサイバー攻撃について、詳しく知りたい方は、以下の記事を参考にしてください。

内部不正
テレワーク環境では、従業員が第三者の目の届かない場所で業務を行うため、不正の発見が遅れやすくなります。特に深刻なのが、従業員による意図的な情報持ち出しです。営業リストや顧客データをUSBや私用クラウドへ保存し、転職先や競合企業に持ち出して流用するケースは後を絶ちません。また、業務上知り得た情報をSNSや外部チャットツールで漏らす行為も情報漏洩に該当します。
このような内部不正の疑いがある場合、証拠の改ざんを防ぐため、速やかにフォレンジック調査を実施し、機密情報が外部に漏洩していないか確認することが重要です。専門家と連携し、調査結果に応じて法的対応などを実施しましょう。
テレワークによる情報漏洩の疑いがある場合の対処法
テレワークによる情報漏洩の疑いが発覚した場合、以下の対処法で調査から関係者への報告を行いましょう。
システムや端末をネットワークから切り離し
情報漏洩の兆候が見られた際は、まず被害の拡大を防ぐため、対象端末やシステムを直ちにネットワークから切り離す必要があります。社内ネットワークへの接続を遮断することで、外部へのデータ流出やマルウェア感染の拡大を最小限に抑えることが可能です。
また、隔離後は対象端末の電源を切らず、現状を保ったまま次の対応へ進むことが重要です。誤った対処により証拠が消失する恐れがあるため、慎重な対応が求められます。
証拠となるログ・データを保全する
漏洩の原因究明や責任追及には、証拠となるアクセスログや通信履歴、端末の操作記録の保全が不可欠です。特に電源を切るとRAMの揮発性データが消失する可能性があるため、保全は専門知識をもって慎重に行う必要があります。
ログの取得・保全には専用のツールや保全の手順を必要とするため、社内のみの対応が難しい場合は、フォレンジック調査が可能な外部の専門家への相談が推奨されます。

フォレンジック調査を行う
情報漏洩の原因や影響範囲を技術的に明らかにするには、フォレンジック調査の実施が有効です。
フォレンジック調査とは、パソコンやスマートフォン、ネットワーク機器などに残された操作履歴やログデータを専門的に解析し、不正行為や情報漏洩の有無などを明らかにする調査手法です。
USBの接続履歴やファイルのコピー・削除・クラウドへのアップロードなどの痕跡を客観的に把握でき、必要に応じて削除されたデータを復元して調査する場合もあります。
証拠を損なわずに調査を行うためには、高度な知識と専門機材が必要となるため、信頼できる調査会社への依頼が望ましいでしょう。調査結果は報告書としてまとめられ、社内対策や法的対応にも活用されます。
漏洩が発覚したら顧客や個人情報保護委員会へ報告する
万一、個人情報や機密データの漏洩が明らかになった場合は、速やかに関係各所へ報告を行う必要があります。特に「個人情報の保護に関する法律」では、漏洩が判明した際に個人情報保護委員会と本人への報告が義務付けられています。
報告が遅れた場合、企業の信頼失墜や法的責任を問われる恐れがあります。状況の把握と再発防止策を明確にした上で、誠実かつ迅速な対応が企業としての信頼を守る鍵となります。

テレワークによる情報漏洩に有効なのはフォレンジック調査

テレワークの実施によって個人情報や機密情報といった情報が漏洩した可能性がある場合、事実確認の手段として「フォレンジック調査」が有効です。
近年の情報漏洩や情報持ち出しはパソコンやスマートフォンを用いて行われることが多い傾向にあります。一方で情報漏洩の痕跡はパソコンやスマートフォンに残りやすいですが、データの性質状、改ざんや上書き削除などのリスクと隣り合わせです。
データも証拠として警察や裁判所などの公的機関に提出可能なため、正しい方法で全ての証拠を収集するためにも、フォレンジック調査は専門家にお任せすることをおすすめします。
デジタルデータフォレンジック(DDF)なら、インシデントごとに専門の調査チームが調査にあたるため、不正アクセスによる情報漏洩から、内部不正による情報持ち出しまで、実態に合わせて幅広く調査することが可能です。
警察・捜査機関の累計ご相談件数も、現在までに395件以上*受けており、捜査に協力したことによる感謝状を頂いた実績もございます。
匿名でのご相談にも対応しております。法人のお客様には、Web打ち合わせでのご対応も可能ですので、情報持ち出し調査のご相談がすぐに必要な方は、以下の連絡先よりお気軽にご連絡ください。
*期間:2017年8月1日〜
テレワークによる情報漏洩を予防する方法
テレワークによる情報漏洩を予防する方法について以下の方法が有効とされます。
ログ管理を行う
従業員の操作ログやアクセスログを適切に記録・監視することで、異常な行動や不正な情報持ち出しの兆候を早期に検出できます。ログ管理は、事後の証拠としても活用でき、セキュリティインシデント対応において重要な役割を果たします。
ログの保存期間の設定や改ざん防止、ログレビューの体制整備も不可欠です。SIEMなどの専用ツールを活用することで、効率的かつ自動化された監視体制の構築が可能になります。
最新のセキュリティ製品を導入する
テレワーク環境では、エンドポイントセキュリティやEDRなどの最新ツールを導入することが有効です。ウイルス対策ソフトだけでなく、不審な挙動を検知してアラートを出す仕組みが求められます。
また、ゼロトラストモデルの導入により、接続端末やユーザーを常に検証する体制を構築することで、不正アクセスのリスクを大幅に低減できます。
情報セキュリティの規則を見直す
テレワークの実施にあたっては、既存のセキュリティポリシーが現実に即しているかを定期的に見直す必要があります。私物端末の利用可否、データ保存先の制限、業務アプリの使用ルールなどを明確に定め、従業員に対して周知徹底を図ることが重要です。
曖昧なルールは不正やミスの温床となるため、実態に合わせた具体的かつ厳格な規則への改定が求められます。
フリーWi-Fiの使用を避ける
外出先で業務を行う際、カフェや駅などのフリーWi-Fiに、安易に接続するのは危険です。これらのネットワークは暗号化が不十分で、第三者に通信内容を傍受されたり、中間者攻撃(MITM)を受けたりする可能性があります。
業務でネットワークに接続する場合は、信頼できるモバイルルーターやVPNを使用することが推奨されます。社内でも「安全な通信経路の確保」をルール化することが大切です。
端末の管理方法を見直す
業務用端末の紛失や盗難を防ぐため、管理方法を徹底する必要があります。ログインには多要素認証を導入し、OSやソフトウェアは常に最新の状態に保ちましょう。
また、持ち出し端末にはリモートロックやデータ消去機能を備えたMDM(モバイルデバイス管理)を導入し、端末を物理的・論理的に保護できるよう、万全な管理体制を整備しましょう。
機密情報にアクセス制限をかける
すべての従業員に一律のアクセス権を与えるのではなく、業務上必要な範囲に限定することで、不正利用や誤操作による情報漏洩を防ぐことができます。
アクセス制御はID管理システムやファイルサーバの権限設定などで実施可能です。退職者や異動者に対する権限の見直しを怠ると、意図せぬ漏洩リスクにつながるため、定期的な棚卸しも重要です。
よくある質問
対応内容・期間などにより変動いたします。
詳細なお見積もりについてはお気軽にお問い合わせください。
専門のアドバイザーがお客様の状況を伺い、概算の見積りと納期をお伝えいたします。
可能です。当社は特定の休業日はございません。緊急度の高い場合も迅速に対応できるように、365日年中無休で対応いたしますので、土日祝日でもご相談下さい。
もちろん可能です。お客様の重要なデータをお取り扱いするにあたり、当社では機密保持誓約書ををお渡しし、機器やデータの取り扱いについても徹底管理を行っております。また当社では、プライバシーの保護を最優先に考えており、情報セキュリティの国際規格(ISO24001)およびPマークも取得しています。法人様、個人様に関わらず、匿名での相談も受け付けておりますので、安心してご相談ください。