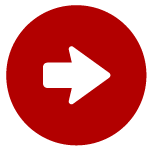職務怠慢は、企業活動において大きな損失を生み出す要因の一つです。従業員による継続的な業務不履行やサボリ行為が放置されると、生産性の低下や職場のモラル崩壊を招く可能性があります。ただし、従業員に対して適切な処分を行う場合でも、法的手続きを軽視した対応は、不当解雇などの重大なリスクにつながります。
本記事では、職務怠慢に該当する行為の見極め方、調査方法、処分の基準について、詳しく解説します。ぜひ参考にしてください。
\累計3.9万件の相談実績 24時間365日 相談受付/
目次
職務怠慢とは
職務怠慢(しょくむたいまん)とは、従業員が与えられた業務を故意に怠る、または誠実に取り組まない状態を指します。
たとえば、勤務中に正当な理由なく私的な行動を繰り返す、または業務命令に従わず業務を放棄する行為などが該当します。職務怠慢の状態が継続すると、組織の秩序に悪影響を及ぼすため、懲戒処分の対象となる可能性があります。
懲戒処分を適用できるケースと適用できないケース
職務怠慢に該当する行為であっても、すべての業務不履行が懲戒処分に直結するわけではありません。労働契約法や民法により、従業員には業務を誠実に遂行する義務があります。
義務を故意に怠った場合、債務不履行とみなされる可能性があります。
ただし、処分ができるかどうかは、状況に応じて異なります。
懲戒処分が適切とされるケース
- 正当な理由なく無断欠勤・遅刻を繰り返している
- 注意・指導を受けても改善せず、継続的に勤務態度が悪い
- 職場の秩序を乱すような言動や私的行動が業務中に常態化している
懲戒処分が不適切とされるケース
- 体調不良や家庭の事情など、やむを得ない事情がある
- 業務に支障はあるが、指導やフォロー体制が未整備であった
- 企業側からの具体的な改善指示がなかった、または曖昧だった
つまり、職務怠慢と見なされる行為があっても、処分の判断では、「継続性」「悪質性」「指導歴の有無」が重要な判断材料となります。
企業にとって職務怠慢が問題になる理由
職務怠慢が放置されると、企業運営に以下のような悪影響が生じる恐れがあります。
- 業務の遅延や成果物の質の低下
作業が進まず、納期や品質に影響が出る - チームのモチベーション低下
努力する社員に不公平感が生じ、士気が下がる - 顧客や取引先との信頼損失
対応の遅れやミスが外部評価の低下につながる - 職場の秩序崩壊
ルールを守らない社員が許容されると、組織の規律が乱れる - 離職率の上昇
真面目な社員が離職し、採用・教育コストが増大する
上記ようなリスクを避けるためには、職務怠慢が疑われる行動に対して、早期かつ適切な対応が必要です。
就業規則と懲戒事由との関係
会社には懲戒処分を行う権限がありますが、権限には制限があります。もし会社がその権限を濫用した場合、労働契約法第15条に基づき、懲戒処分は無効となることがあります。
労働契約法第15条では、「使用者が労働者に対して懲戒処分を行う場合、その懲戒が労働者の行為の性質や態様、その他の事情を考慮して客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当でないと認められる場合、その権利を濫用したものとして懲戒処分は無効となる」と定めています。
また、就業規則は労働基準法第89条に基づき、労働基準監督署に届け出る必要があります。届け出が行われていない場合、懲戒規定の適用が無効となることがあります。
一般的に、懲戒処分が有効となる要件としては以下が挙げられます。
- 就業規則に明確な規定がある
規則内に「職務怠慢」「業務命令違反」などの懲戒事由が記載されている - 対象行為が該当する
問題行動が、就業規則の具体的な条項に該当すると判断できる - 就業規則が労働基準監督署へ届出済み
就業規則は正式に届け出が行われている必要がある - 従業員に周知が行われている
就業規則の内容が社内で共有され、誰でも確認できる状態にある
上記の要件が欠けている場合、懲戒処分が無効と判断される可能性があります。処分を行う際には、記録の整備と法的根拠の明確化が重要です。
出典:e-Gov
\累計3.9万件の相談実績 24時間365日 相談受付/
職務怠慢とみなされる具体的な行為方法
職務怠慢かどうかは、労働契約で定められた業務時間や職務の履行義務を果たしているかで判断されます。従業員が業務を意図的に実行しない場合、債務不履行として法的責任を問われる可能性があります。
以下に、職務怠慢として扱われる代表的な行動と、判断基準について解説します。
遅刻・欠勤・勤務態度の悪化
従業員には、所定労働時間を守り、職務を誠実に遂行する義務があります。正当な理由のない遅刻や無断欠勤、著しく不適切な勤務態度が続く場合、懲戒処分の対象になる可能性があります。
故意や過失により会社へ損害を与える行為
従業員が故意または重大な過失により会社に損害を与えた場合、法的には「不法行為責任(民法709条)」または「債務不履行責任(民法415条)」が問われる可能性があります。
たとえば、タクシー運転手が居眠り運転で、乗客の安全確保義務を怠り、交通事故を起こした場合は「債務不履行」「不法行為」の2要件が成立し、解雇事由になりえます。
ただし、過重労働など企業側の責任が認められる場合には、処分の有効性が否定されることもあります。民法第415条でも「債務者の責めに帰することができない事由」があるときは、損害賠償の責任を免れるとされています。
懲戒処分を検討する際は、従業員の行為だけでなく、職場環境や管理体制も含めて総合的に判断することが重要です。
勤務実態と異なる残業代の不正請求
実際の業務と合致しない残業申請も職務怠慢と見なされることがあります。勤務時間中に業務を行わず、私的行動に費やしていたにもかかわらず残業申請を行った場合には、虚偽申請として懲戒対象となる可能性があります。
以前は立証が難しいケースも多くありましたが、現在では以下のような証拠により実態の可視化が可能です。
- パソコンの操作ログや業務アプリの使用履歴
- 業務日報や報告書の整合性
- GPSやWi-Fiログなどの位置情報
たとえば、業務時間中にネットカフェなどへ長時間滞在していた履歴があれば、不正申請を否定する根拠になります。客観的な証拠をもとに判断することが、適正な処分を行ううえで不可欠です。
\累計3.9万件の相談実績 24時間365日 相談受付/
職務怠慢への適切な対応
従業員に職務怠慢が見受けられる場合、感情に流されることなく、客観的な事実と就業規則に基づいた対応が求められます。とくに懲戒処分を検討する場面では、事前に適切な指導と改善の機会を与えることが、法的リスクを避けるうえで重要です。
本人への注意・指導
最初の段階では、該当する従業員に対し、明確な注意と業務に対する指導を行うことが必要です。指導過程では、本人の業務姿勢の見直しを促しながら、抱えている悩みや事情にも耳を傾けることが望まれます。
指導を実施する際には、以下の手順に沿って進めると効果的です。
- 業務実態や勤務態度を記録し、具体的な問題点を整理する
- 面談を行い、現状と改善の必要性について丁寧に説明する
- 指導内容を文書で残し、従業員の署名を得て記録として保管する
手順により、従業員に対して明確な期待を示すとともに、改善の機会を提供できます。万一、懲戒処分に移行する場合でも、記録が処分の正当性を証明する材料となります。
懲戒処分へ進む前の対応
注意や指導を重ねても改善が見られないときは、懲戒処分を検討する段階に入ります。ただし、処分の妥当性を担保するには、必要な準備と手続きを怠らないことが前提です。準備不足での対応は、たとえ内容に正当性があったとしても、不当と判断される恐れがあります。
懲戒処分に進む場合は、社内で必要な対応を適切に整備することが重要です。
- 出勤記録や業務報告、指導記録など、職務怠慢に関する証拠を整理する
- 就業規則に記載された懲戒事由に該当するかを確認する
- 人事部門や第三者委員会を含めた関係者による公正な判断を行う
対応手順を丁寧に進めることで、処分の正当性を明確にし、不当解雇と判断されるリスクを防ぐことが可能になります。
\従業員の職務怠慢を発見した方へ/
職務怠慢に対する懲戒処分と企業側リスク
職務怠慢が明らかになった場合でも、安易に解雇を行うことは適切ではありません。手続きに不備があれば、不当解雇として訴訟リスクが発生し、企業にとって大きなダメージとなります。
懲戒処分の種類と適用の基準
懲戒処分を行うには、労働法と就業規則に基づいた正当な理由と手続きが必要です。
労働契約法第16条では「合理的な理由を欠き、社会通念上相当と認められない解雇」は無効とされており、慎重な判断が求められます。
懲戒処分には、次のような段階があります。
- 注意・指導
業務態度の改善を促す初期対応 - 戒告
口頭や文書による厳重注意 - 譴責(けんせき)
始末書の提出を求める正式な処分 - 減給・出勤停止
金銭的・就業的な制限を伴う中度の処分 - 懲戒解雇
重大な違反行為に対する最終手段
いきなり懲戒解雇に踏み切るのではなく、段階的な対応を経て処分を判断することが、法的にも企業倫理としても求められます。
また、懲戒処分が正当とされるためには、以下のような要件を満たしていることが必要です。
- 就業規則に懲戒の種類と対象となる行為が明記されている
- 違反行為がその規定に該当している
- 証拠や記録によって事実が裏付けられている
- 従業員に改善の機会が与えられている
たとえば、以下のような行為は「解雇相当」と判断される可能性があります。
- 指示命令に繰り返し従わない
- 業務に支障をきたすほどの勤務態度不良
- 職場での暴言・暴力
- 重要な業務上の義務違反
- 企業機密の漏洩や不正取得
ただし、該当する行為があっても、直ちに解雇できるわけではありません。実際の判断では、個別の事実関係や就業規則との整合性、過去の対応履歴などを踏まえたうえで、慎重に対応する必要があります。
解雇が「無効」と判断されるケース
適切な手続きを踏まずに職務怠慢を理由に解雇した場合、労働者側から不当解雇として争われる可能性があります。
以下のようなケースでは、解雇の無効が認められています。
- 注意・指導を十分に行わず、いきなり解雇した
- 就業規則に基づかない理由で懲戒処分を行った
- 労働者に責任があるとは言いきれない状況だった
懲戒解雇の有効性を裏付けるには、日常の記録・指導経緯・業務ログといった客観的証拠が必要です。
不当解雇による企業側のリスク
職務怠慢を理由に従業員を解雇した際、手続きや理由に不備があると「不当解雇」として法的責任を問われる可能性があります。不当解雇と認定されると、企業は以下のようなリスクを負うことになります。
- 復職命令
地位確認請求によって、裁判所から職場への復職が命じられる可能性があります。 - 未払い賃金の支払い
解雇期間中の給与を遡って支払う義務が生じる場合があります。 - 損害賠償請求
精神的苦痛などを理由に慰謝料の支払いが命じられることもあります。 - 企業イメージの悪化
訴訟報道や評判の低下により、採用や取引に悪影響が出るおそれがあります。 - 社内モラルの低下
不当な処分が明るみに出ると、社員の士気や信頼にも悪影響を及ぼします。
リスクを防ぐためには、客観的な証拠をもとに法令に沿った対応が重要です。
\従業員の職務怠慢を発見した方へ/
職務怠慢を証明するための調査方法
職務怠慢が疑われた場合、懲戒処分の正当性を示すためには、客観的な証拠に基づく調査が不可欠です。以下では、調査の基本的な流れと活用できるデータについて解説します。
通報や苦情の確認
職務怠慢の兆候は、同僚からの通報や上司の報告で発覚することがあります。調査の第一歩として、寄せられた情報を記録に残し、事実確認を行う準備を進めます。
業務内容の確認
対象となる従業員の職務内容や役割を明確にし、実際に未遂行であった業務を洗い出します。目標や担当範囲も含めて整理することで、職務怠慢の具体性を裏付けやすくなります。
勤務実態の調査
勤務記録や業務日報、パソコンの操作履歴などを通じて、実際の労務提供状況を検証します。以下のような資料が調査に活用できます。
- タイムカード(打刻申請表)
- 注意指導文書・始末書
- 懲戒処分通知書
- 従業員のパソコン
- スマートフォンや業務用端末
社内端末の画面を記録するツールを併用すれば、勤務中の行動を客観的に把握できます。
調査で参考にすべきデータの分類
以下は酌量の余地があるかを、数字で表せる「定量的なデータ」と、勤務態度など「定性的なデータ」の両方の側面から参照します。
- 業務に与えた影響
- 無断欠勤・遅刻の回数
- 過去の戒告や懲戒処分履歴
- 遅刻・欠勤の理由や動機
- 反省の姿勢や改善意欲
- 指導後の勤務状況
- 過去の判例や社内規定との照合
デジタルフォレンジック調査の有効性
IT機器の操作履歴や通信ログを分析するデジタルフォレンジックは、職務怠慢の証明に非常に有効です。特にテレワーク環境では、実際に業務が行われていたかを可視化する手段として活用が広がっています。
たとえば、操作がなかった時間帯や、私的な端末利用のログが取得できれば、労務不履行を裏付ける証拠として利用できます。
本人への事情聴取
最後に、本人から直接ヒアリングを行います。勤務状況や遅刻・欠勤の背景、改善意欲などについて聞き取りを行い、内容を記録として残します。公平性を保つため、事情聴取には複数名で立ち会うことが望まれます。
職務怠慢の調査を行う場合、専門業者に相談する

社内不正・横領・情報持ち出し・職務怠慢のような問題が発生した場合、どのような経路で、どのような情報が漏えいしたのか、被害の全容を正確に把握する必要があります。適切な調査によって原因究明を行うためにも、フォレンジック調査の専門家に相談することが重要です。
特に、法的手続きが絡むケースや被害が広範囲に及ぶ場合は、専門家の力を借りることで被害の最小化と信頼性の高い証拠の収集が可能です。
>情報漏えい時の個人情報保護委員会への報告義務とは?詳しく解説
当社では、インシデント対応のプロが初動対応から、専門設備でのネットワークや端末の調査・解析、調査報告書の提出、ならびに報告会によって問題の解決を徹底サポートします。
フォレンジックサービスの流れや料金については下記からご確認ください。
【初めての方へ】フォレンジックサービスについて詳しくご紹介
【サービスの流れ】どこまで無料? 調査にかかる期間は? サービスの流れをご紹介
【料金について】調査にかかる費用やお支払方法について
【会社概要】当社へのアクセス情報や機器のお預かりについて
デジタルデータフォレンジックの強み
デジタルデータフォレンジックは、迅速な対応と確実な証拠収集で、お客様の安全と安心を支える専門業者です。デジタルデータフォレンジックの強みをご紹介します。
累計相談件数39,451件以上のご相談実績
官公庁・上場企業・大手保険会社・法律事務所・監査法人等から個人様まで幅広い支持をいただいており、累積39,451件以上(※1)のご相談実績があります。また、警察・捜査機関から累計395件以上(※2)のご相談実績があり、多数の感謝状をいただいています。
(※1)集計期間:2016年9月1日~
(※2)集計機関:2017年8月1日~
国内最大規模の最新設備・技術
自社内に40名以上の専門エンジニアが在籍し、14年連続国内売上No.1のデータ復旧技術(※3)とフォレンジック技術でお客様の問題解決をサポートできます。多種多様な調査依頼にお応えするため、世界各国から最新鋭の調査・解析ツールや復旧設備を導入しています。
(※3)第三者機関による、データ復旧サービスでの売上の調査結果に基づく。(2007年~2017年)
24時間365日スピード対応
緊急性の高いインシデントにもいち早く対応できるよう24時間365日受付しております。
ご相談から最短30分で初動対応のWeb打合せを開催・即日現地駆けつけの対応も可能です。(法人様限定)自社内に調査ラボを持つからこそ提供できる迅速な対応を多数のお客様にご評価いただいています。
デジタルデータフォレンジックでは、相談から初期診断・お見積りまで24時間365日体制で無料でご案内しています。今すぐ専門のアドバイザーへ相談することをおすすめします。
職務怠慢を防ぐために企業ができる対策
職務怠慢を未然に防ぐには、働きやすい環境の整備と適切な従業員管理が重要です。以下には、企業が取り組める具体的な施策をご紹介します。
労働環境の見直しとモチベーション管理
職務怠慢の背景には、働きづらい環境や不透明な評価制度が関係している場合があります。社員が安心して能力を発揮できる環境を整えることが、怠慢の防止につながります。
- コミュニケーションの促進
意見交換や相談ができる風土を作り、上下関係を問わず連携しやすい職場にします。 - ワークライフバランスの確保
労働時間や休暇制度を整え、過度な負担を減らします。 - 研修制度の充実
社員が成長を実感できるよう、スキルアップの機会を提供します。 - 健康管理の強化
健康診断やストレスチェックを定期的に実施し、心身の不調を早期に察知します。 - 前向きな職場の雰囲気
チームワークを促進し、助け合いの文化を育みます。
適切な報酬体系も、やる気の維持に欠かせません。
- 目標達成に応じた報酬
個人やチームの実績に応じてインセンティブを支給します。 - 業績連動型の昇給・賞与
会社の業績と連動させた公平な評価制度を構築します。 - 柔軟な働き方の導入
フレックスタイムやテレワーク制度を導入し、多様な働き方を尊重します。 - 福利厚生の充実
住宅手当や健康保険、退職金制度などを整え、安心感を提供します。
就業規則・評価制度の整備
ルールが曖昧であると、従業員の意識に差が生まれます。次のような明確な規定を整備することで、公平な評価と秩序維持が可能になります。
以下のようなルール整備が必要です。
- 出勤時間や勤務態度に関する基準の明記
- 業績評価や成果に対する明確な指標
- 懲戒処分に該当する行為とその基準の明示
明確な基準を示すことで、従業員も自身の行動を見直しやすくなり、モチベーション維持にも効果があります。
問題行動に対しては指導による改善
職務怠慢が確認された際は、ただちに懲戒処分に進むのではなく、まずは指導によって改善を図る姿勢が大切です。
以下は改善を促す具体的対応です。
- 面談を通じて現状の課題や本人の状況を丁寧に聞き取る
- 必要に応じて業務の見直しや支援体制を強化する
- 指導内容を文書にまとめて記録し、再発防止に活用する
指導対応に通じて従業員との信頼関係を維持しながら、公正な改善を促すことができます。
まとめ
職務怠慢は、組織の生産性や職場環境に深刻な影響を与える問題です。対応を誤れば、不当解雇や労働紛争といったリスクも伴います。
まずは、就業規則や評価制度を明確にし、日常的なコミュニケーションやサポート体制を整えることが重要です。そして、問題が発生した際には、記録の整備、証拠の確保、適切な手続きをもって対応する必要があります。
「怠慢行為の確認」「指導記録の整備」「証拠に基づく判断」の3点を徹底することで、企業としての正当性を保ちつつ、労務リスクを最小限に抑えることが可能です。
対応が難しい場合や判断に迷う状況では、デジタルフォレンジック調査の活用が有効です。客観的な証拠をもとに判断を行うことで、公平で確実な対応につながります。
\従業員の職務怠慢を発見した方へ/
よくある質問
対応内容・期間などにより変動いたします。
詳細なお見積もりについてはお気軽にお問い合わせください。
専門のアドバイザーがお客様の状況を伺い、概算の見積りと納期をお伝えいたします。
可能です。当社は特定の休業日はございません。緊急度の高い場合も迅速に対応できるように、365日年中無休で対応いたしますので、土日祝日でもご相談下さい。
もちろん可能です。お客様の重要なデータをお取り扱いするにあたり、当社では機密保持誓約書ををお渡しし、機器やデータの取り扱いについても徹底管理を行っております。また当社では、プライバシーの保護を最優先に考えており、情報セキュリティの国際規格(ISO24001)およびPマークも取得しています。法人様、個人様に関わらず、匿名での相談も受け付けておりますので、安心してご相談ください。