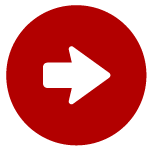パソコンが勝手に操作されたり、見覚えのないアプリケーションが動いていたりする場合は、第三者による遠隔操作の可能性があります。
遠隔操作が行われている状況を放置すると、認証情報や個人データが盗まれたり、重要なファイルが破壊されたりといった深刻な被害へと発展する危険性があります。さらに、業務や私生活にも大きな支障が出ることが考えられます。
- 「サポート詐欺に誘導されて遠隔操作ソフトをインストールしてしまった」
- 「リモートアクセスツール(TeamViewerなど)が勝手に起動している」
上記のような偽警告を使ったサポート詐欺や偽アプリのインストールなど、遠隔操作の手口は様々で、被害を防ぐためにも、適切な対処が必要です。もし、自力での対応が難しいと感じた場合には、遠隔操作された場合はすぐに専門家に相談しましょう。
目次
パソコンが遠隔操作で乗っ取られた状態を放置する危険性
パソコンが遠隔操作されているにもかかわらず何も対処を行わなかった場合、状況は時間の経過とともに急速に悪化していきます。攻撃者は、すでに自由に操作可能な状態であるため、保存データの盗難や改ざん、不正アクセスの連鎖など、多くの二次被害が発生するおそれがあります。
遠隔操作を放置することで広がるリスク
- 保存されている個人情報や業務データが外部に送信される
- ネットバンキングやクレジットカード情報が悪用される
- メールアカウントやSNSが乗っ取られ、なりすまし被害が発生する
- 盗まれた情報がダークウェブで売買される
- 自分のパソコンがサイバー攻撃の踏み台として利用される
遠隔操作された状態のパソコンは、攻撃者にとって非常に価値の高い「攻撃拠点」となっています。被害を受けるだけでなく、他人への加害行為に利用されるリスクもあるため、放置することは絶対に避けるべきです。
ネットワークの遮断、マルウェアスキャン、パスワード変更といった初期対応をすみやかに行い、必要に応じてフォレンジック調査会社への相談を検討してください遠隔操作された状態での使用を続けることは、情報漏洩や金銭的被害、さらには刑事事件に発展するおそれがあります。
違和感を感じた時点で、すぐに行動に移すことが被害を最小限に食い止める鍵となります。対応が困難な場合には、自力で抱え込まず、信頼できる専門家に相談することが最善の選択です。
パソコンが遠隔操作された時にすぐやるべきこと
パソコンが勝手に動く、知らない画面が開いたなど、遠隔操作の疑いがある状況ではパニックに陥るのも無理はありません。ですが、最も大切なのは、まず深呼吸をして落ち着くことです。
遠隔操作は、情報漏洩や金銭被害、不正アクセスといった深刻なリスクにつながる可能性がある重大なインシデントです。
早急に対応すれば被害を最小限に抑えられますが、状況によってはセキュリティソフトだけでは対応しきれない場合もあります。
そのため、まずは以下の手順に沿って落ち着いて対処し、必要に応じてフォレンジック調査会社への相談も検討することが安全確保への近道です。
ネットワークを切断する
外部からの操作を遮断するため、まずはインターネット接続をオフにすることが基本となります。接続を維持したままでは、情報の流出や追加操作が続く危険性があります。
- Wi-Fi接続:タスクバーまたは設定画面からWi-Fiをオフにする
- 有線接続:LANケーブルを物理的に抜く
- ルーター利用:ルーター本体の電源をオフにする
通信を切断することで、被害の拡大を防ぐ第一歩となります。
セキュリティソフトでスキャンする
接続を切ったあとは、セキュリティソフトでパソコン全体をスキャンします。不正プログラムやマルウェアが潜伏している可能性があるため、駆除が必要です。
セキュリティソフトでスキャンを行っても「何も検出されなかった」からといって、安心するのはまだ早いです。
近年では、高度に偽装されたマルウェアやリモート操作ツール(RAT)がセキュリティソフトの検出をすり抜けるケースも少なくありません。
なぜ検出されないのか?
- 暗号化・難読化されたコードによって、既知のウイルス定義と一致しない
- OSやアプリの正規プロセスを模倣することで、一般的な挙動と見分けがつかない
- ユーザー権限を奪取した後に自己削除・証拠隠滅を図るタイプのマルウェアも存在
被害の兆候があるにも関わらず、セキュリティソフトが何も見つけられなかった場合は、すでにログレベルでの調査が必要な段階かもしれません。
専門の調査会社に相談する
遠隔操作の被害が広範囲に及ぶ場合や、どのような情報が漏洩したかを正確に把握する必要がある場合には、フォレンジック調査によるデータ収集と分析が不可欠です。
フォレンジック調査でできること
- 不審なリモートアクセスのログやマルウェア実行履歴の復元
- 削除・隠蔽されたファイルの復元
- 通信履歴・IPアドレスの追跡による攻撃元の特定
- 漏洩した可能性のあるデータやその範囲の明確化
フォレンジック調査では、パソコンやネットワークの使用履歴、アクセスログ、不審なファイルの痕跡などを専用ツールで解析し、情報漏洩の有無や被害の全容を明らかにします。調査結果は、企業内の対応指針や法的手続きにおいても非常に重要な役割を果たします。
法人利用なら特に重要な判断材料に
企業や団体が使用しているパソコンの場合、被害の大きさだけでなく「誰が責任を持ってどう対処したか」が問われます。
そのため、初期化や自己流の対応はかえってリスクを高める結果になりかねません。
- 内部不正や従業員の関与が疑われる場合
- 機密情報の外部流出の可能性がある場合
- 被害内容を報告書としてまとめる必要がある場合(社内報告・法的対応)
とくに、法人の機密情報漏洩や従業員による内部不正が疑われる場合には、パソコンの初期化や自己判断での対応は避け、必ず専門のデジタル調査会社に依頼することが重要です。
当社は累計約46万件ものサイバーインシデント対応実績があり、情報漏えいを引き起こさないための対策方法など豊富な知見を有しています。当社のサイバーセキュリティ専門家が、事前の予防から万が一の対応まで徹底サポートいたします。
24時間365日で無料相談を受け付けておりますので、お気軽にご相談ください。
✔どこに依頼するか迷ったら、相談実績が累計39,451件以上(※1)のデジタルデータフォレンジック(DDF)がおすすめ
✔データ復旧業者14年連続国内売上No.1のデータ復旧技術(※2)とフォレンジック技術で他社で調査が難しいケースでも幅広く対応でき、警察・捜査機関からの感謝状の受領実績も多数。
✔相談からお見積まで完全無料
※1 累計ご相談件数39,451件を突破(期間:2016年9月1日~)
※2 データ復旧専門業者とは、自社及び関連会社の製品以外の製品のみを対象に保守及び修理等サービスのうちデータ復旧サービスを専門としてサービス提供している企業のこと
第三者機関による、データ復旧サービスでの売上の調査結果に基づく。(集計期間:2007年~2020年)
パソコンが遠隔操作された後対応しなければならない事
フォレンジック調査によって不正アクセスや遠隔操作の痕跡が判明した場合、次に行うべきは「被害の封じ込め」と「情報漏洩に伴う各種手続き」です。
以下に、調査後に速やかに取るべき対応をまとめます。
すべての重要アカウントのパスワード変更
メールやSNS、金融機関のログイン情報が流出した可能性があるため、すべてのパスワードを変更する必要があります。安全なデバイスを使用して操作してください。
- Google / Microsoft アカウント
- SNS(LINE, Facebook, Instagram, X など)
- オンラインバンキング・証券・決済アプリ(PayPay、楽天銀行など)
- ECサイト(Amazon、楽天市場、Yahoo!など)
- 企業用の業務アカウント(社内システム・VPN・メール)
あわせて、二段階認証(2FA)を有効にすることも必須です。
会社・関係者への報告(法人・業務利用の場合)
知らないうちにインストールされている遠隔操作ソフトが存在する場合があり、削除することで、不正アクセスにより遠隔操作を遮断できます。
業務用のパソコンや共有アカウントが被害にあった場合、社内コンプライアンスに基づいた報告が義務となります。
- 上長や情報セキュリティ担当部署への報告
- 顧客情報が漏洩した可能性がある場合、取引先への通知とお詫び
- 情報漏洩報告書や社内事故報告書の作成
特に、従業員の内部不正が疑われる場合は、証拠の保全と法的対応の準備が必要になります。
金融機関・関係機関への連絡
個人・法人問わず、万が一の金銭的被害に備えて、口座情報やカード情報を登録している各機関に速やかに連絡しましょう。
- 銀行:不審な送金や残高変動がないか確認/口座凍結の相談
- クレジットカード会社:カード再発行・不正利用の停止
- スマホキャリア/プロバイダ:契約情報の変更、不正通信の確認
金融機関側も不正アクセスの通報を受けることで、補償の対象となる場合があります。
同様のリスクを防ぐための再発防止策
再発を防ぐためには、次のようなセキュリティ対策を見直すことが重要です。
- セキュリティソフトの導入・更新状況の見直し
- 不要なアプリや拡張機能の削除
- OS・アプリの自動アップデート設定
- パスワードの定期更新ルールの導入(個人も企業も)
操作できるうちに、大切なファイルや業務データは別媒体にバックアップしておきましょう。データ損失を未然に防ぐための対応として有効です。
まとめ
特に企業や組織で使用している端末では、情報漏洩・内部不正・業務データの流出といった影響が、信頼や損失に直結する重大リスクとなります。
セキュリティソフトの検出をすり抜けるケースもありますので、専門のフォレンジック調査会社による客観的で技術的な解析が、最も信頼できる手段です。
そんなときは、自己判断に頼らず、専門家の力を借りることが、被害の最小化と再発防止への第一歩となります。
自力で対応できない場合はフォレンジック調査の専門業者に依頼する

ハッキングや不正アクセス、ウイルス感染、情報漏えいなどの問題が起きた際、自分だけでの対応が難しいと感じたら、迷わずフォレンジック調査の専門業者に相談しましょう。
どこから侵入され、どんな情報が漏れたのかを正しく把握することが重要です。特に、被害が大きい場合や情報が悪用された疑いがある場合は、専門家によるフォレンジック調査を実施することで、被害の拡大を未然に防ぐ有効な対策につながります。
信頼できる業者を選び、早めに動くことが、トラブルを最小限に抑えるポイントです。
フォレンジックサービスの流れや料金については下記からご確認ください。
【初めての方へ】フォレンジックサービスについて詳しくご紹介
【サービスの流れ】どこまで無料? 調査にかかる期間は? サービスの流れをご紹介
【料金について】調査にかかる費用やお支払方法について
【会社概要】当社へのアクセス情報や機器のお預かりについて
デジタルデータフォレンジックの強み
デジタルデータフォレンジックは、迅速な対応と確実な証拠収集で、お客様の安全と安心を支える専門業者です。デジタルデータフォレンジックの強みをご紹介します。
累計相談件数39,451件以上のご相談実績
官公庁・上場企業・大手保険会社・法律事務所・監査法人等から個人様まで幅広い支持をいただいており、累積39,451件以上(※1)のご相談実績があります。また、警察・捜査機関から累計395件以上(※2)のご相談実績があり、多数の感謝状をいただいています。
(※1)集計期間:2016年9月1日~
(※2)集計機関:2017年8月1日~
国内最大規模の最新設備・技術
自社内に40名以上の専門エンジニアが在籍し、14年連続国内売上No.1のデータ復旧技術(※3)とフォレンジック技術でお客様の問題解決をサポートできます。多種多様な調査依頼にお応えするため、世界各国から最新鋭の調査・解析ツールや復旧設備を導入しています。
(※3)第三者機関による、データ復旧サービスでの売上の調査結果に基づく。(2007年~2017年)
24時間365日スピード対応
緊急性の高いインシデントにもいち早く対応できるよう24時間365日受付しております。
ご相談から最短30分で初動対応のWeb打合せを開催・即日現地駆けつけの対応も可能です。(法人様限定)自社内に調査ラボを持つからこそ提供できる迅速な対応を多数のお客様にご評価いただいています。
デジタルデータフォレンジックでは、相談から初期診断・お見積りまで24時間365日体制で無料でご案内しています。今すぐ専門のアドバイザーへ相談することをおすすめします。
よくある質問
対応内容・期間などにより変動いたします。
詳細なお見積もりについてはお気軽にお問い合わせください。
専門のアドバイザーがお客様の状況を伺い、概算の見積りと納期をお伝えいたします。
可能です。当社は特定の休業日はございません。緊急度の高い場合も迅速に対応できるように、365日年中無休で対応いたしますので、土日祝日でもご相談下さい。
もちろん可能です。お客様の重要なデータをお取り扱いするにあたり、当社では機密保持誓約書ををお渡しし、機器やデータの取り扱いについても徹底管理を行っております。また当社では、プライバシーの保護を最優先に考えており、情報セキュリティの国際規格(ISO24001)およびPマークも取得しています。法人様、個人様に関わらず、匿名での相談も受け付けておりますので、安心してご相談ください。