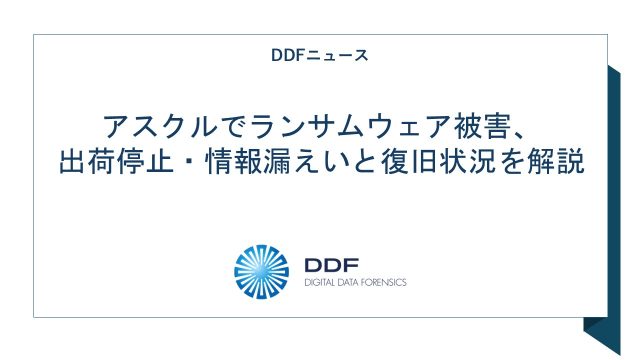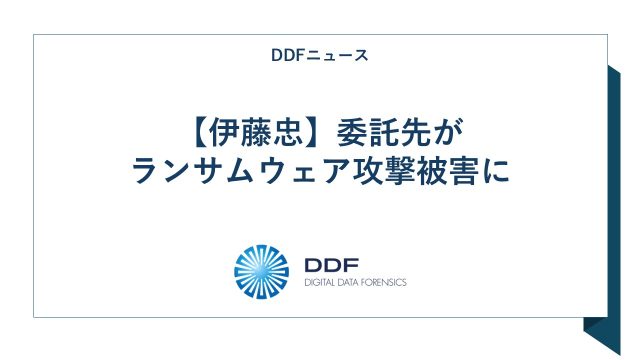「スマホのカメラが乗っ取られるなんて本当にあるの?」と疑問に思う方は多いでしょう。スマホカメラ乗っ取りとは、悪意のある第三者が不正にカメラへアクセスし、利用者に気づかれないまま撮影・録音を行う行為を指します。主にマルウェア感染やOSの脆弱性悪用によって発生します。
この記事では、スマホカメラが乗っ取られる可能性や具体的な被害事例、そして効果的な対策までをわかりやすく解説します。
目次
スマホのカメラは本当に乗っ取られるのか?
結論から言えば、スマホのカメラは技術的に「乗っ取られる可能性があります」。ただし、その実現にはいくつかの条件が揃う必要があり、誰にでも簡単に起きるわけではありません。

AndroidとiOSの違い
一般的に、Androidは自由度が高い反面、セキュリティ面ではリスクも高めです。非公式アプリが簡単に導入できるため、マルウェアに感染するリスクが上がります。
一方で、iOSは審査が厳しく、基本的にApp Store経由でしかアプリを入れられないため安全性は高いですが、それでも過去には脆弱性を突かれたケースが存在しています。
スマホのカメラ乗っ取りは、誰にでも起こりうる現実的なリスクです。ただし、ほとんどのケースではユーザー側の油断や不注意がきっかけになっています。つまり、しっかりと対策をしていれば、リスクは大きく減らすことができるのです。

スマホのカメラ乗っ取りの主な手口
スマホのカメラが乗っ取られる原因には、いくつかの典型的な手法があります。
このセクションでは、どのような方法でカメラが不正に操作されるのかを具体的に解説します。被害を未然に防ぐためにも、まずは攻撃者のやり口を正しく理解しておくことが重要です。
1. マルウェアを仕込んだアプリ
悪意のあるアプリにカメラのアクセス権限を与えると、ユーザーが気づかないうちに写真や動画を撮影されることがあります。特にAndroid端末では、Google Play以外の非公式ストアからアプリをインストールする際に注意が必要です。

2. OSやアプリの脆弱性を突いた攻撃
ゼロデイ脆弱性と呼ばれる、開発者もまだ把握していないシステム上のバグを狙って、アクセス権なしにカメラを操作するケースがあります。これは高度な技術を持つ攻撃者によるもので、一般の個人が狙われる可能性もゼロではありません。

3. フィッシングや偽装画面を使った手口
「顔認証のためにカメラの許可が必要です」と表示され、正規のアプリを装ってユーザーにアクセスを許可させる手口もあります。アプリの見た目が本物そっくりに作られていることも多く、注意が必要です。

スマホのカメラを乗っ取られた場合に起こる被害
スマホのカメラが乗っ取られると、どのようなリスクや被害が生じるのでしょうか?このセクションでは、実際に起こりうる被害を4つのケースに分けて解説します。現実味のあるリスクを知ることで、防御意識を高めるきっかけになります。
無断での盗撮・盗聴
スマホのカメラやマイクを使って、ユーザーの自宅や職場の様子、私的な会話などが記録されてしまう可能性があります。本人が気づかないうちに撮られた写真や動画が流出する危険性もあるため、非常に深刻です。
個人情報の流出
撮影された映像や音声から、住所、勤務先、通学ルート、家族構成などが特定されるケースがあります。情報がSNSなどに拡散されてしまうと、社会的信用の失墜にもつながりかねません。
脅迫や詐欺の材料にされる
「この写真をネットに公開されたくなければ金を払え」といったリベンジポルノや、なりすましによる詐欺行為につながるリスクもあります。個人の生活が破壊される事例も報告されています。
他の個人情報への侵入
カメラが乗っ取られているということは、スマホ全体が不正に操作されている可能性もあります。連絡先、SNS、クレジットカード情報、写真フォルダなど、他の重要なデータも同時に盗まれる危険性があります。
スマホカメラの乗っ取りを防ぐ5つの対策
リスクを防ぐためには、日頃からの意識と具体的な行動が欠かせません。このセクションでは、スマホカメラの乗っ取りを防ぐために実践すべき対策を5つに分けて紹介します。
1. アプリのインストールに注意する
信頼できないアプリは極力インストールしないようにしましょう。特に、公式ストア以外からのアプリはリスクが高くなります。
2. アクセス権限の管理を徹底する
アプリに与えているカメラやマイクの権限を定期的に確認し、不必要なアクセスは制限するようにしましょう。
3. OSとアプリを常に最新に保つ
アップデートを怠ると、既知の脆弱性を放置することになります。定期的に更新することでセキュリティを強化できます。
4. セキュリティアプリを活用する
スマートフォンにもウイルス対策アプリを入れておくことで、異常な挙動を検出できる場合があります。
5. カメラを物理的にカバーする
シールやカバーでレンズを覆っておけば、万が一の乗っ取りにも備えられます。地味ですが効果的です。
また、スマホのカメラが乗っ取られるリスクは、決して他人事ではありません。
誰でも被害に遭う可能性があり、特にセキュリティ意識が低いユーザーほど狙われやすい傾向にあります。
日頃から「不要なアプリは入れない」「アクセス権限を見直す」「アップデートを怠らない」といった基本的な対策を徹底することで、被害を未然に防ぐことが可能です。
「自分は大丈夫」と思い込まず、日常的にセキュリティ意識を持つことが何よりの防御になります。
乗っ取られたかも?と思ったときの対応方法
スマホのカメラが乗っ取られているかもしれない…。そう感じたとき、個人で判断するのは非常に難しいものです。安易に対処しようとすると、証拠を消してしまったり、被害を拡大させるリスクもあります。
そんなときこそ、スマホやセキュリティに詳しい専門家やサポート窓口に相談することが、被害を最小限に抑える最も安全な方法です。このセクションでは、被害を最小限に抑えるための初動対応について解説します。
- 使用していないアプリや不審なアプリを削除する
- スマホの設定から、カメラやマイクの使用履歴・権限を確認する
- SNSやGoogleアカウントなどのログイン履歴を調べる
- 必要であれば、スマホを初期化し、データを復旧する
- 信頼できるセキュリティ専門業者やキャリアに相談する

自力で対応できない場合はフォレンジック調査の専門業者に依頼する
 ハッキングや不正アクセス、ウイルス感染、情報漏えいなどの問題が起きた際、自分だけでの対応が難しいと感じたら、迷わずフォレンジック調査の専門業者に相談しましょう。
ハッキングや不正アクセス、ウイルス感染、情報漏えいなどの問題が起きた際、自分だけでの対応が難しいと感じたら、迷わずフォレンジック調査の専門業者に相談しましょう。
どこから侵入され、どんな情報が漏れたのかを正しく把握することが重要です。特に、被害が大きい場合や情報が悪用された疑いがある場合は、専門家によるフォレンジック調査を実施することで、被害の拡大を未然に防ぐ有効な対策につながります。
信頼できる業者を選び、早めに動くことが、トラブルを最小限に抑えるポイントです。
フォレンジックサービスの流れや料金については下記からご確認ください。
【初めての方へ】フォレンジックサービスについて詳しくご紹介
【サービスの流れ】どこまで無料? 調査にかかる期間は? サービスの流れをご紹介
【料金について】調査にかかる費用やお支払方法について
【会社概要】当社へのアクセス情報や機器のお預かりについて
デジタルデータフォレンジックの強み
デジタルデータフォレンジックは、迅速な対応と確実な証拠収集で、お客様の安全と安心を支える専門業者です。デジタルデータフォレンジックの強みをご紹介します。
累計相談件数47,431件以上のご相談実績
官公庁・上場企業・大手保険会社・法律事務所・監査法人等から個人様まで幅広い支持をいただいており、累積47,431件以上(※1)のご相談実績があります。また、警察・捜査機関から累計409件以上(※2)のご相談実績があり、多数の感謝状をいただいています。
(※1)集計期間:2016年9月1日~
(※2)集計機関:2017年8月1日~
国内最大規模の最新設備・技術
自社内に40名以上の専門エンジニアが在籍し、17年連続国内売上No.1のデータ復旧技術(※3)とフォレンジック技術でお客様の問題解決をサポートできます。多種多様な調査依頼にお応えするため、世界各国から最新鋭の調査・解析ツールや復旧設備を導入しています。
(※3)第三者機関による、データ復旧サービスでの売上の調査結果に基づく。(2007年~2023年)
24時間365日スピード対応
緊急性の高いインシデントにもいち早く対応できるよう24時間365日受付しております。
ご相談から最短30分で初動対応のWeb打合せを開催・即日現地駆けつけの対応も可能です。(法人様限定)自社内に調査ラボを持つからこそ提供できる迅速な対応を多数のお客様にご評価いただいています。
デジタルデータフォレンジックでは、相談から初期診断・お見積りまで24時間365日体制で無料でご案内しています。今すぐ専門のアドバイザーへ相談することをおすすめします。
よくある質問
対応内容・期間などにより変動いたします。
詳細なお見積もりについてはお気軽にお問い合わせください。
専門のアドバイザーがお客様の状況を伺い、概算の見積りと納期をお伝えいたします。
可能です。当社は特定の休業日はございません。緊急度の高い場合も迅速に対応できるように、365日年中無休で対応いたしますので、土日祝日でもご相談下さい。
もちろん可能です。お客様の重要なデータをお取り扱いするにあたり、当社では機密保持誓約書ををお渡しし、機器やデータの取り扱いについても徹底管理を行っております。また当社では、プライバシーの保護を最優先に考えており、情報セキュリティの国際規格(ISO24001)およびPマークも取得しています。法人様、個人様に関わらず、匿名での相談も受け付けておりますので、安心してご相談ください。
この記事を書いた人